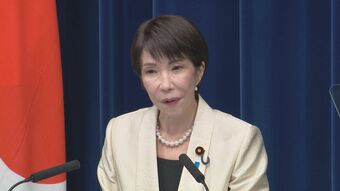認知的不協和の影響力
討論(および情報提供や論争一般)が効果的でない理由としてルブラノが注目するのは「認知的不協和(cognitive dissonance)」である。この概念は、社会心理学者のレオン・フェスティンガーが唱えた概念で、自分の信念や行動に矛盾する情報に直面した際に感じる、しばしば無意識の心理的不快感を意味する。
認知的不協和を感じると、人は、新しい情報によって矛盾を軽減し、自分の信念を合理化しようとする。例えばタバコを吸っている人が「タバコは健康に悪い」という情報に触れた場合、認知的不協和を解消するために、「喫煙は人をリラックスさせてくれる」等、ほかの情報によって認知的不協和を低減しようとする。
フェスティンガーはこの概念を、予言を信じるカルト信者たちが、予言が外れた後に一層信じるようになり、熱心に布教を始めるという現象から考案した(注6)。
ルブラノによれば、これと類似したことがアメリカの大統領選で起きていた。2024年にトランプが複数の罪で有罪判決を受ける前、共和党支持者の17%しか「犯罪者は大統領になることができるべきだ」とは信じていなかった。しかし、有罪判決直後、その割合は58%に急上昇した。
大統領は犯罪者であってはならないという信念と、トランプが大統領であるべきだという信念という矛盾を調和させるため、共和党支持者の大多数は前者の信念を変更したのである。
実際、共和党支持者はトランプが有罪判決を受けたほぼすべての事項に関する見方を変更し、不倫を隠蔽するために金銭を支払うこと、またはビジネス記録を改竄することが道徳的に間違っていると感じる人の割合は減少した。
このルブラノが挙げる例は、兵庫県知事の支持者たち、公文書改竄の疑惑があった故安倍晋三元総理の支持者たちを理解する上でも参考になりそうだ。私の推測では、こうした認知的不協和は、「推し活」の心理全般で、ファンや支援者の信念の強化に影響している。
ファンや支持者の多くは、自分の「推し」が苦境に立たされ、非難されればされるほど、一層支持するようになるだろう。もちろん認知的不協和に陥った時に、自分の信じてきたことが事実ではないと知って、支持を止める人たちも存在するが、むしろ不協和を解消するために支持や信念を強める人たちが大勢いることを私たちは現に目撃している。
以上の例が示すのは、一見理性的な選挙活動に見える政策討論さえ、「推し活」を強化することにしかならないということだ。つまり「推し活選挙」は良くない、政策について議論するべきだと言って討論を行なったところで、支持者たちはそこで得た新たな情報を自分が支持する政治家について客観的に考える材料にせず、認知的不協和という形で解消してしまうのである。
認知的不協和を産むSNS空間
推し活以外にも、スピリチュアルにハマる人、仮想通貨にハマる人、陰謀論にハマる人など、特定の信念を強める人がコロナ禍以降増えている印象がある。こうした小さなカルトが無数生まれている現在の状況は、認知的不協和を生みやすいSNS環境と無関係ではないと私は推測している。
かつては自分に同調的な意見しか見えないフィルターバブルが問題視されていたSNS環境だが、「バズった」投稿が「おすすめ」などに表示される現在のアルゴリズムでは、意見の対立や炎上は常に起こっていて、自分もまた非難に晒される可能性があるということも常に可視化されているように見える。
また改めて考えてみれば、人はSNSにアクセスするたびに、数えきれないほどの人たちが意見を表明している渦中に足を踏み入れるわけだが、こうした状況は、リアルな物理的な空間ではまずあり得ないことだ。
SNS利用者はSNS空間で生じる認知的不協和・負荷を常に抱えることで、自分が意識している以上に疲労や不安を感じているはずだ。その結果、認知的不協和を解消し、負荷を減らすために、ますます何かを信じ、盲目的に推す人が増えるのはごく自然なことに思われる。
ルブラノは、SNS環境でいわゆる右派がうまく立ち回り支持を集めていることを指摘しているが、実際、トランプ大統領のみならず副大統領のJ・D・ヴァンスもまたSNS巧者なのは間違いがない。
彼らのSNS発信では、自分たちを被害者に見立てることで支持者を団結させるというやり方、そして極端な発言、暴力的な発言が目立つ。およそ大統領や副大統領にふさわしくない発言が生む認知的不協和は、彼らに対する支持をむしろ強化するのかもしれない。SNS空間では極端なことを言う人が、嫌悪もされるが同時に人気を集めてインフルエンサーになる。私たちはそのことをすでに幾つもの例によって知っているはずだ。