「てんさい」という作物をご存じでしょうか?別名「砂糖大根」とも呼ばれる“砂糖”の原料です。このてんさいから作る砂糖=「てんさい糖」をリンゴやそばに次ぐ県の特産にしたいと取り組む男性がいます。

善光寺のお膝元で菓子店を営む藤田治(ふじた・おさむ)さん。看板商品の鯉焼きは、県産食材にこだわっています。

藤田治さん:「小麦粉は長野県産100%、花豆のあんこも長野県産。でも、砂糖だけがどうしても…」
お菓子作りに欠かせない砂糖は、6割ほどが輸入品です。さらに、砂糖の主な原料であるてん菜(主に北海道)とサトウキビ(沖縄・鹿児島など)は、国内では、北海道や沖縄などの一部の地域でしか作られていません。
そんな中、藤田さんは、寒冷地でも育つ「てん菜」なら…と信州産の可能性を見出しました。
藤田治さん:「信濃町と北海道が年間平均気温が同じなので、北海道で出来るなら長野でも出来るのではないかと。砂糖がないとお菓子屋は成り立たないんで、逆に砂糖さえあればなんでも出来るという。じゃあ自分で作るかと」
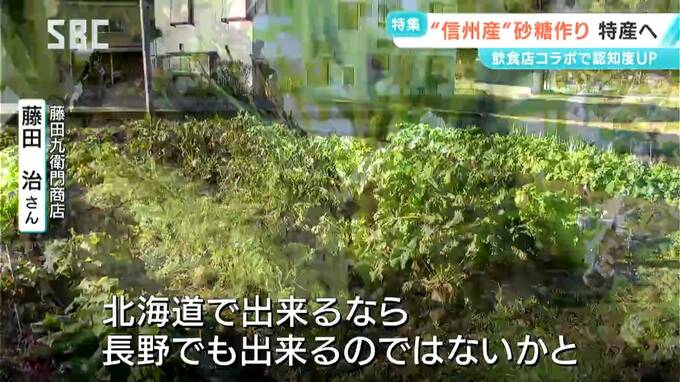
そうして、3年前にスタートした信州産の「砂糖」作り。
クラウドファンディングで集めた資金で種などを購入し、プロジェクトに賛同したメンバーと県内各地で栽培を始めました。
栽培が比較的簡単で、北海道産よりも糖度の高いものが採れるなど、成果も出てきています。
現在は、県内12市町村で合わせて400キロを目標にてん菜を栽培。藤田さんは、その一部を譲り受け、「てんさい糖」を作っています。
藤田治さん:「こっちが王滝村でこれが塩尻。一生懸命同じ作り方でやっているが全然違う色になって味も全然違う。去年までは食べると甘いね、美味しいね。でも、エグミがすごすぎて、もういいやみたいな。でも今年作ったやつは、いけるね、美味しいね。もう1個いけるねっていう感じ」

石灰を入れるタイミングや量など、てんさい糖の作り方はまだ研究段階ですが、最近では、店頭で味を確かめてもらっています。
客:「しっかり甘さがありますね。でもさっぱりしてる感じ…」
藤田治さん:「黒糖と同じ作り方で作っているんですけど、黒糖って後味とパンチがすごいんですけど、てんさい糖はパンチもあるんだけどすっと消えていく感じです」














