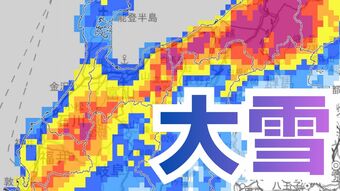ミャンマーの軍事クーデターから4カ月が過ぎた昨年5月、出入国在留管理庁(入管庁)は、日本に住むミャンマー人の救済策を打ち出した。本国の情勢不安を理由に、希望すれば在留と就労を認めるという「緊急避難措置」だった。あれから1年半。「緊急避難」とは名ばかりに、救いの手から取り残された人たちがいる。当事者を追った。
■夫の急死で来日した母と4歳の息子は、いま…
「日本のみなさま、ミャンマーの人たちを助けてください」
10月の休日の午後、都心のJR駅前で、ミャンマー少数民族チンの人たちが民主化運動への募金を呼び掛けていた。その中に愛称・ノリさん(53)の姿があった。行き交う人が時折、立ち止まっては声を掛けていく。中には千円札を入れる年配者も。「ありがとうございます」。ノリさんは、募金箱を抱えて深々と頭を下げた。
ノリさんと高校三年生の一人息子(17)に話を聞いた。
「パパもいない。(私は)いつも泣いている。いま全部大変」。ノリさんの言葉は切実だった。話が込み入ってくると、チンの言葉に変わるので、「3割ほど話せます」という息子が日本語に訳してくれた。
ノリさんの夫は民主化運動に関わり、英語教師のかたわらアウン・サン・スー・チーさんの著作「恐怖からの自由」をチン語に翻訳するなどしていた。2001年、軍の手が迫っていることを知り、単身、国境を越えてインドに逃れた。05年9月、「日本は民主主義の国だからと」思って来日した。だが09年に急死、ノリさんは、ミャンマーから4歳の息子を連れて日本に飛び、葬儀に参列した。
日本滞在中に夫の死がミャンマーのメディアで報じられ、軍が自宅を捜索したとの知らせが入る。親族から帰国を断念するよう説得され、日本での難民申請に踏み切った。
母子は「特定活動」の在留資格を得て、ノリさんは焼き肉店で働いた。息子は学校に通い、高校では奨学金も受け取れた。しかし難民は2回、不認定に。昨年、在留資格が更新されず退去強制手続が始まり、「非正規滞在」となった。入管施設への収容を解かれる「仮放免」が認められているので、自宅で暮らしてはいるが、就労は禁止、健康保険にも入れない。日本やアメリカにいる親戚からの支援が頼みの綱だ。

■修学旅行の積立金で払った授業料
「勉強、頑張ってます」。ノリさんは、大学進学を目指して努力する息子に目を細める。とはいえ学費は気掛かりでならない。在留資格を失ったために住民票や所得証明書が提出できなくなり、奨学金は打ち切られた。取り急ぎ、来年3月に高校を卒業するまでの授業料9万円を、コロナ禍で中止になった修学旅行の積立金13万円から支払った。いずれ奨学金の貸与分の返済が始まる。
息子は「親戚に助けてもらっているけれど、収入がないので…」と不安をもらす。「仮放免」の更新手続きも心配だ。3カ月おきに入管に出向かなければならず、次々回は2月の入試時期と重なる。
いま、3回目の難民申請をしている。ノリさんの出身地チン州では、国軍と抵抗勢力との激しい衝突が続く。兄はCDM(市民不服従運動)のリーダーとして活動しているため、自宅は軍に没収され、同居の母や兄の家族は避難生活を続ける。ノリさんは「難民と認められないのは悲しい」と肩を落とした。
■来日21年、何もできない
群馬県館林市にはミャンマーの少数民族ロヒンギャの人たちが多く住む。日本に来てすでに21年になる男性(48)を訪ねた。
ロヒンギャは仏教徒が多数のミャンマーでは少数派のイスラム教徒だ。ミャンマーの法律では、不法移民として先住民族から除外されて国籍を認められてこなかった。2017年には治安部隊による武力弾圧で70万人以上が隣国バングラデシュに逃れ、国連調査団は「ジェノサイド(民族大量虐殺)の深刻なリスクの下にある」と報告している。
男性は、14歳で民主化運動に加わり、26歳で来日、これまで入管に3回収容された。現在は「仮放免」の身で、在留資格のある妻、小2と4歳の男の子と暮らす。「奥さんの給料だけでは足りないが、いまは何もできない」。3回目の難民申請中だ。
信用していた日本人から頼まれて、ATMからカードでお金を引き出したことが罪に問われ、執行猶予の付いた有罪判決を受けたことがあったという。日本語が読めないので、本人のカードと思い込んでいたと語る。
「日本の法律を守って、仕事して、家族で幸せに生きたい。難民と認められなければ、私には行く場所がない。」
■「緊急」に適用されない「緊急避難措置」
入管庁が「緊急避難措置」を打ち出して1年半近くになるのに、ノリさんやロヒンギャの男性には適用されていない。
昨年5月に入管庁が発表した際には、希望する人には在留や就労を認め、難民認定申請者には「審査を迅速に行い、難民該当性が認められる場合には適切に認定し、認められない場合でも緊急避難措置として在留や就労を認める」と明言していた。
昨年は、少ないながらもミャンマー人32人が難民と認定された。入管庁の資料では、今年3月末までに約4600件の在留資格が認められた。
しかし、ミャンマー人の難民申請を多数扱う渡辺彰悟弁護士によると、多くの「非正規滞在」の難民申請者について可否の判断が出ていないという。ノリさんやロヒンギャの男性もその中に含まれる。
入管庁は制度上、難民かどうかの結論が出るまでは在留資格に手を付けられないとしている。皮肉なことに、不認定であっても判断が出さえすれば、在留や就労への道は開けるのだが、ノリさんたちは難民申請が継続中なので「緊急避難措置」は適用されない。1年半もの間、途中経過も知らされず、ただひたすら待つしかない状況に置かれてきた。
渡辺弁護士は「少数民族で複数回の申請者が多く、3回、4回目の人も少なくない。『緊急避難』と大きな期待を抱かせて、何も応えないのは精神的な拷問に近い」と憤る。
■「難民申請の審査を迅速に」ではなかったのか?
サッカーワールドカップ予選でミャンマー代表として来日し、試合で軍のクーデターに抗議の意思を表明した男性は、申請から2カ月で難民認定された。アフガニスタン政変後、日本に退避した日本大使館の現地職員と家族98人は、申請から1カ月たたずに認定の結論が出た。
「審査を迅速に」と言っていたのに、なぜ1年半も結論が出ないのか。昨年、批判を受けて廃案となりながら、いまだに政府が成立に固執する入管法改正の動きと関係があるのだろうか。
現在の法では難民申請中は送還されないが、問題の改正案には、ノリさんたちのように3回以上の難民申請者を送還可能にする条項が含まれていた。これに対して批判が噴出した。というのも日本は難民の認定に高いハードルを設けているため、認定率は欧米諸国と比べて極端に低い。不認定となった人たちは、もし他の国で申請していたら難民と認められていた可能性がある。本来ならば難民と認めるべき人たちを、申請の回数で門前払いして、命の危険が伴う母国に送還するのか…。UNHCR(国連難民高等弁務官事務所)も「重大な懸念」を表明した。
3回以上申請をしているミャンマー人について、一転して難民と認めるケースが出てしまえば、改正案の必要性は大きく揺らぐ。だから結論を先延ばしにしているのだろうか。あるいは、救済から取り残すことによって苦しい状況に追い込み、難民申請自体を諦めさせる意図があるのか。そんなことまで考えてしまう。
8月末、渡辺弁護士は入管庁を訪れて、難民申請の結果を早く出すように求めた。担当者は遅れの理由には答えず、「特に急ぐ人は?」と問い返してきたため、「みんな急いでいる。全員、9月中に結論を出してほしい」と迫ったという。
いまだに、動きは、ない。
神田和則(元TBSテレビ社会部長)