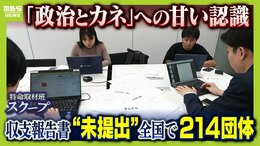山口県下関市の住宅密集地で起きた火災では、少なくとも20棟が全焼しました。
なぜここまでの被害が出たのか。
住宅密集地の火災の傾向と、被害を防ぐポイントを消防に聞きました。
 7日、山口県下関市長崎町で発生した住宅密集地の火災。
7日、山口県下関市長崎町で発生した住宅密集地の火災。
現場は、JR下関駅から約1キロの木造の住宅が密集する地域。
消防車が入れるような道路はなく、ホースを何本もつなげて放水。
 消防車が17台出動し火は約3時間15分後に消し止められました。
消防車が17台出動し火は約3時間15分後に消し止められました。

消防と警察で実況見分を行い、少なくとも20棟が全焼し、焼失面積は約2100平方メートルだったことが分かりました。このほかにも複数の空き家や住宅が焼けたとみられます。
県内ではこれまでにも、住宅が密集する場所での火災が発生しています。
2011年、山口市の中心商店街から火が出て、9棟が全半焼。
2018年には新山口駅近くの繁華街で7棟が全半焼しました。
共通するのは、住宅や飲食店が密集している点です。
山口市消防本部の山下消防司令補は、住宅と住宅の距離や気象状況が関係するといいます。

山口市消防本部 予防課 予防担当 山下康一 消防司令補
「まず1つは密集しているところ、建物と建物の距離が近いので、炎を受けやすいとかということももちろんあると思いますし、乾燥しやすいとか気象状況ですね。乾燥している状況であったり、風が強いとか気象条件もかなり反映してくるんじゃないかと思います」
7日、下関で火災が発生したときは、県内全域に乾燥注意報が発表され、吹き上がりの風が吹くなど、火が燃え広がりやすい条件がそろっていたとみられます。
また、斜面は火が上に上がっていくことから、延焼するスピードも速くなります。
住宅密集地で火災が起きた場合は、どうすればいいのでしょうか。
山口市消防本部 予防課 予防担当 山下康一 消防司令補
「初期消火と通報と避難というのをどこが今必要なのかを把握してもらって、対応してもらうというところで、地域のコミュニティで考えてもらう対策をとってもらうと密集地での対応も少しはいい方に行くのではないかと思います」
住宅が密集しているからこそ周りの人と声を掛け合って避難をする。
基本的な火災への対応が人や建物への被害を減らすことにつながるといいます。
しかし、一番重要なのは「火事を起こさない」こと。
火の取り扱いにより一層注意をすることが大切です。