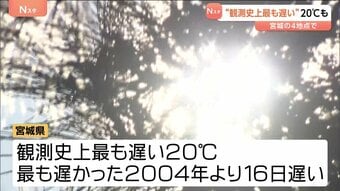中国国家統計局は24日、今年7-9月期の実質GDP(国内総生産)が、前年同期比で3.9%増だったと発表しました。この統計、もともとは共産党大会開催中の18日に発表予定でしたが、直前に突然の発表延期となり、「数字が良くないので『忖度』して延期したのだろう」という憶測が出ていました。
GDPという最も重要な経済指標の発表が、説明もなく延期されるようなことは、「普通の国」ではあり得ないことです。ともあれ、3.9%という数字が、習近平政権3期目のスタートには「ふさわしくない」「不都合な」数字であったことは、間違いありません。
「今年5.5%成長の目標達成は不可能か」
中国の今年の成長目標は、5.5%前後です。これまで8%以上の成長が当たり前だった中国にすれば、5.5%は十分、『安定飛行』に減速した経済の姿です。しかし、1-3月期が4.8%、4-6月期がコロナの主要都市ロックダウンによって、わずか0.4%、そして7-9月期も3.9%と、一度も5.5%に遠く届いておらず、このままでは今年の目標は、絵に描いた餅で終わりそうです。元来、計画経済の国で政府見通しの未達などあってはならないことです。
中身を見ても、5年に一度の共産党大会を前に景気対策の観点からインフラ投資こそ、8.6%増だったものの、中国恒大集団の事実上の破綻に代表される不動産バブルの崩壊から不動産開発投資はマイナスで、肝心の個人消費も低調なままです。1-9月の小売売上高は0.7%増に過ぎません。これは中国が依然として『ゼロコロナ』政策をとり続けていることが大きな要因で、外食やサービスなどの営業は実質的に大きく制限されていると言います。定期的なPCR検査が義務付けられていることも大きな負担で、働き手が検査のために月に何度も半日・一日と潰されてしまい、仕事にならないと言います。
「それでもやめない『ゼロコロナ』政策」
それでも『ゼロコロナ』政策をやめないのは、コロナ発生当初の武漢『鎮圧』が習近平政権の「成功」とされなければならないからでしょう。そして『ゼロコロナ』政策による行動規制が、ある種、統制の道具としても機能しているのでしょう。東京財団主席研究員の柯隆さんによれば、すでにPCR検査に巨大利権ができていることも、『ゼロコロナ』をやめられない理由の一つだそうです。『ゼロコロナ』政策は、今後も繰り返し、中国経済の足を引っ張りそうです。
習近平政権3期目の人事は、共産党幹部のほとんどが習近平氏に近い人たちで占められました。特に首相に就任予定のナンバー2の座には、上海のロックダウンで批判された李強氏がおさまりました。多様性とは程遠い、金太郎飴のような『一強体制』では、政策が行き詰まった際の方向転換は容易ではありません。しかも、この政権は、これまでの「改革開放」より「社会主義堅持」を唱えています。体制「堅持」の観点から国有企業優先の姿勢は明確で、逆に成長をけん引してきた民間企業への規制や締め付けは一層強化されています。ついこの間まで我が世の春を謳歌していた、アリババなどの中国IT大手企業の時価総額は急減しています。
「低成長化は新たなチャイナリスク」
現段階の中国経済にとって、民間企業の活力の最大化や、雇用や所得の増大を通じた国内消費主導経済への移行が、何より重要であることは誰の目にも明らかです。非効率な国有企業に資源を配分し、過剰な公共投資を繰り返すことは、全く逆方向です。
中国の成長率は、2021年7‐9月期に4.9%増と、コロナ直撃期を除き、初めて5%を割り込み、世界に衝撃を与えました。それからまだ1年しか経っていません。中国経済の低成長化は予想以上のスピードで進んでおり、習政権3期目の政策によって、さらに加速される気配です。世界は、低成長という新たな『チャイナリスク』にも向き合うことになりそうです。
播摩 卓士(BS-TBS「Bizスクエア」メインキャスター)