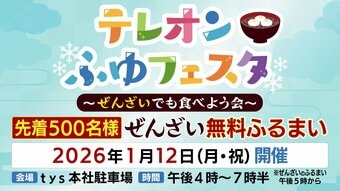さあ、待ちに待った給食です。
合掌直後のことでした。
お皿を持った児童が先生のもとに集まっていきます。

大歳小では、時間内に食べられそうにない場合、箸を付ける前に児童が自主的にごはんやおかずを戻します。
そして、そのあとにもっと食べたい児童に分けます。
クラス全体で食べ残しゼロを目指す、これも「SDGs」です。
給食の内容にも変化がありました。
農林水産省の調査などによると、牛乳を瓶で提供する学校は1970年代には全国で9割を占めていましたが
今や8割以上が紙パックに代わっているそうです。
瓶を製造する業者の減少などが理由だそうです。
さらに、「日本型食生活」の普及を目指す農林水産省の取り組みなどでパンが減り、ごはんが増えています。
変化は、挙げれば切りがないようで、平成生まれの記者もジェネレーションギャップを感じる取材となりました。
今の社会は、情報があふれ、多様性が認められ始め、便利な道具に満ちていますが、選択肢が多い分、「これさえやっておけばいいよ」というものが昔よりも減っているのではないでしょうか。
昔より「自分で考えて選ぶこと」、「自分らしさを見つけること」がより求められているのかなと感じました。
そんな現代を生きる子どもたちや現場を応援したい、子どもたちが社会の変化の中で安心して学校生活を送れるような環境を整えることも大人の大事な役割ではと、考えました。