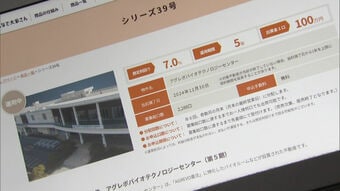「健児」「乙女」…校歌・応援歌はどうなる?
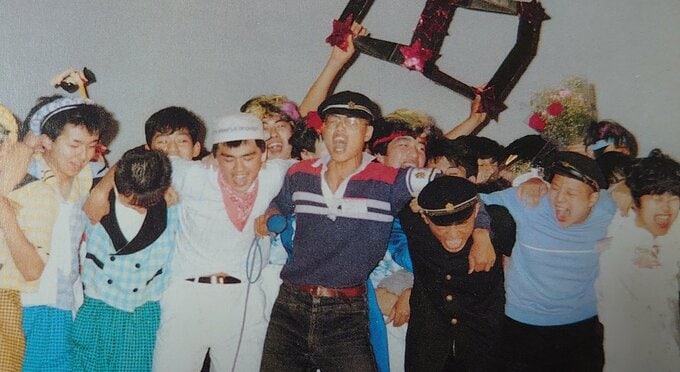
別学出身者として、「共学化の障害になるのでは」と思っているのが、伝統ある校歌や応援歌です。高崎高校の応援歌『翠巒(すいらん)』には、「鍛えし腕を君見よや」「進む健児の意気高し」という歌詞があります。女性が入学したら、「健児」と歌わせるのでしょうか。
よい例が福岡県にあります。黒田藩藩校からの歴史を持つ、1784年創立の福岡県立中学修猷館。戦後に共学となった修猷館高校で、校歌に当たる「館歌」には「集へる健児一千人」という歌詞があります。修猷館の卒業生は「何も考えずに、男子も女子もみな歌っていますよ」と言っていました。
では、女子校を見てみると――。
群馬県立館林女子高校の校歌には、「少女(おとめ)われらは春の草」。埼玉県の浦和第一女子高校は「清らかな空に 乙女子のゆめははてなし」。これを共学化した時に、男子が歌えるか…。ちょっと歌いにくいですね。
でも、男子には「乙女」と歌わせられないのに、女子に「健児」を歌わせるのは、よいのかどうか…。私たちの感覚、実はちょっと変なのではないでしょうか。考えてみると、奥が深い気がします。この理不尽さは、別学に潜む男性優位の思想、私たちの社会が持っている考えの現れかもしれません。こんなことを私はこの数年間考えてきました。
将来の共学化を否定しなくなった

私にとっての高校生活は、男子校以外にはありません。とても楽しくてかけがえのないものです。でも、時代が変わると、同じ校名でも中身はかなり変わっています。高崎高校では、私のころは現役合格率が30%だったのに、今は90%を超えています。少子化で、1学年405人いたのが、今では280人。間違いなく、部活動の数も、参加する生徒数も減っているでしょう。
私たちの時代にはなかった家庭科も始まっています。「私が行っていたころの高崎高校」は、もうないのです。今、私が母校で学んだら、別の学校のように感じると思います。悲しいですが、「そう思うしかない」「そう思ってよいのでは」という気がしています。
「僕らの時代が楽しかったから、同じようにそのままにしておけ」というのも、どうだろうかと思うのです。私の記憶の中には、男子校だった高崎高校の姿がしっかり残っていますが、「後輩が男子でなければ、母校ではない」とは考えていません。「裏切り者」と圧倒的多数の卒業生から言われるのは間違いないと思いますが。
でも、同世代で、私たち生徒会メンバーほど高崎高校に愛着を感じて活動していた生徒たちは他にいません。その一人が今はこう考えている、とお伝えしたかったのです。
心の奥底にずっとある「男ばかりの母校」

戦後、旧制中学・高等女学校から共学の新制高校に変わった時、当時の人たちも同じ悲しさを感じたはずです。でも、共学化しても母校。誰にでもかけがえのない高校時代、これまでに共学化した高校の関係者も複雑な思いを持ちつつ、母校が共学化するのを見守った訳です。別学がゼロになった福島県、秋田県、宮城県でも同じだと思います。「伝統校、進学校だから、別学のままで」というのは、私自身のことも考えて、「理由になっていないのでは」と思っています。
東福岡高校では、中庭で昼食をとる1年生女子を、在校生が教室からずらりと並んで見ていました。「チクショー」「なんで後輩だけ!?」と思っていたのでしょう。映像でその光景を見て、なかなか良かったです。いずれ母校が共学化して、後輩がいい思いをしてもいいですよ。
でも、私の大事な高崎高校は、心の深いところにそのままあります。それはいつまでも男子校のままです。
◎神戸金史(かんべ・かねぶみ)
1967年生まれ。学生時代は日本史学を専攻(社会思想史、ファシズム史など)。毎日新聞入社直後に雲仙噴火災害に遭遇。東京社会部勤務を経てRKBに転職。やまゆり園事件やヘイトスピーチを題材にしたドキュメンタリー映画『リリアンの揺りかご』(2024年)は各種プラットフォームでレンタル視聴可能。最新作『一緒に住んだら、もう家族~「子どもの村」の一軒家~』(2025年、ラジオ)はポッドキャストで無料公開中。