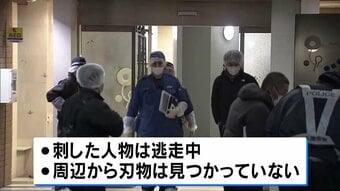■「初級編・中級編・上級編」能力別研修も導入
隙の無い警備を行うため、もう1つ重要なのが警護員の能力向上と育成です。安倍氏銃撃では、そばにいた警護員が銃声の音を識別できなかったり、とっさの危機回避措置を取れなかったりしたことが問題とされました。
警護員は、各道府県警察や管区警察局の学校で受ける指導のほか、警護の実践経験が豊富な警視庁警備部への1年程度の「短期留学」も行われています。また、これまでは能力や経験に差があっても同じ内容の研修を受けていましたが、事件後は、初級、中級、上級など能力別で研修し始めたことに加えて、警視庁警備部への研修生も増やす方針で、いまの2倍を目指すとしています。

これまでも、そしてこれからも、警視庁での研修を軸に全国警察の警護員の育成が続いていくことになります。しかし、警察庁幹部の1人は、こうした警視庁への依存体質が、地方の警察に警護のノウハウを蓄積できなかった原因ではないかと指摘します。
「地方の幹部に、警視庁で研修させればそれで終わりという考えはなかったか。人手不足と組織の縦割りの中で、安易な前例踏襲主義に陥っていなかったか。奈良県警だけの問題ではない」
今後は、警視庁が持つノウハウを地元に帰った研修生たちがどのように根付かせていくかも重要な課題です。
要人警護は「100点か、0点」。安倍元総理を守ることが出来なかった警察、警護員は厳しい批判に晒されました。とは言え、自分の命を盾に人の命を守る警護の仕事は過酷です。
原則、日中は警護対象者と行動を共にし、一緒に食事をすることもあります。他の人には知られてはいけない政治家の秘密を知ることだってあり得るでしょう。
■「ビジネスライク」では務まらない2人の関係
長年警護に携わってきた警察幹部は、警護員と守られる政治家の間には特別な絆があるといいます。
数年前、ある与党の有力政治家が事故を起こした際、警護員は身内である警察幹部から何度となく容体やけがの程度について聞かれても、答えることは無かったと言います。警察庁幹部も、当時のことについて「絆を感じた。ビジネスライクな関係で務まる仕事じゃないよね」と振り返ります。
2度と悲劇を繰り返さないため、警察と警護対象の双方がいかに信頼関係を積み上げていくかが問われ続けることになります。