世代が近い発達障害当事者が困りごとを共有し、助け合う
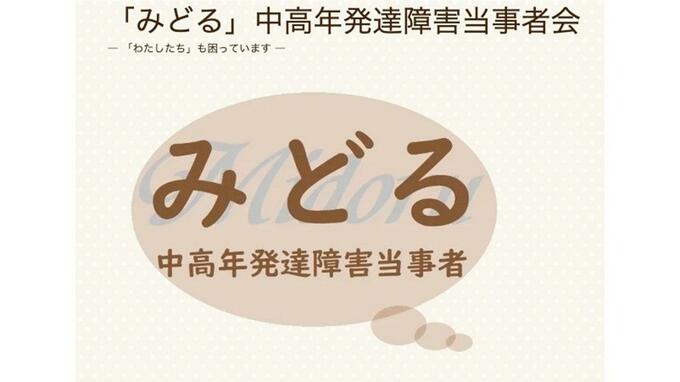
今回は中高年の発達障害当事者会「みどる」を紹介します。
「みどる」は40歳以上の発達障害者の自助、自立のために設立されたピアサポート団体で、毎月1回、第1日曜日か第2日曜日に「茶話会」と呼ばれるイベントを開催しています。
これは基本的に40歳以上で、成人してから障害を診断されたり(成人期診断当事者)、障害を自覚する人が集まって困りごとの相談や情報交換をする会です。
(ケースによっては30代後半でも参加できるそうです)
会が現在の形になったのは2015年で、月に一度の茶話会はすでに100回以上開かれています。
40歳以上の方を中心に開催しているのには理由があります。
近年、成人してから発達障害を診断される20代、30代の方が増え、支援する当事者会、自助会の数も増えています。
ただ、その多くが若い人中心に開催されるそうです。いっぽうで40代、50代、60代の当事者もいて、中高年に特化した当事者会を開催することで、世代が近い人たちの困りごとを共有し、助け合うことをめざしています。
自分も障害を診断されている代表理事の山瀬健治さんに設立目的を聞きました。
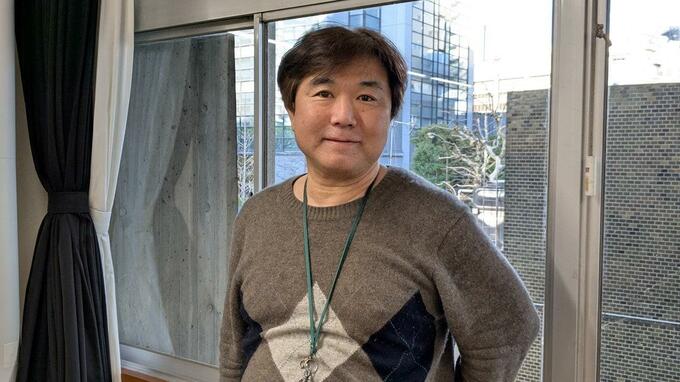
中高年発達障害当事者会「みどる」・代表理事の山瀬健治さん
「当事者会や自助会にいらっしゃる方は増えてますし、そうした会そのものも増えているんですけど、参加者は若い方がボリュームゾーンなんですね。そうすると 40代、50代、場合によると60代の当事者の人って、 20代、30代の人とライフステージが違うので困りごとが全く通じないんですよ。40代以上の当事者って20代、30代の人に自分の話をしにくいこともあります。
実は当事者会のいちばんのメリットは自分はひとりじゃなかったんだ、仲間がいるんだって感じることなのに、仲間と話せるはずの当事者会で、むしろ孤立感を深めてしまうんです。相談しに行ったつもりが自分が聞き役になっちゃうケースもあったりして、それでは本末転倒なので、ライフステージが近い人たちで会を開くほうがピアサポート性が高まるので、 40歳以上に限定して開催させていただいてます」
年齢を重ねると、会社で要職についたり、子供がいたり、親の介護が必要になったり、若い人たちとは違う悩みが出てきます。
そうしたライフステージの違いが、世代間のギャップとして問題になります。
加えて今の中高年が若かった20年前、30年前には「発達障害」という言葉が一般的ではなく、中高年になってから障害を意識したり、診断された人もいて、若い人たちと共有できない困りごともあるそうです。
「みどる」の「茶話会」はそうした中高年世代の語り合い、支え合いの場になっています。















