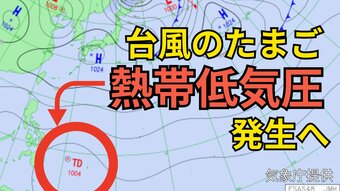焼け跡は、再生できるのか
ーこれから焼け跡はどうなっていくでしょうか?
(東洋産業 大野さん)
「生態系は壊滅してしまいましたが、生き物にとって悪いことばかりでもない場合もあります。壊滅して今は空き家になってしまった環境、新たな命がそこに入り込むチャンスがある、ということです」
「それまで出来上がって、バランスをとっていた生き物たちの営みは豊かではありましたが、新しい生き物が入り込むチャンスは少なかったことでしょう」
「二酸化炭素を吸収する植物が多い山林でも、生物相が出来上がって安定してしまうと、植物が吸収する二酸化炭素と、そこに住む生き物が出す二酸化炭素が同じくらいになってしまうと、見かけ上は二酸化炭素の吸収はできていないことがあります」

「それどころか、その収支がマイナスになることもありえるそうです。二酸化炭素の吸収が多く起こるのは、成長している植物のある場所です」
「なので、山林火災などでその場所の生き物が全滅し、新たに育ち始めた植物たちが、多くの二酸化炭素を吸収してくれるかもしれません。火災で焼けた生き物は肥料になり、新たな生き物の栄養にもなります」
「ちなみに山林火災は、落雷のような自然現象でも起こるわけですが、火災があるとそのあとにいち早く芽吹いてくる植物もいます。山林火災を種の生存のサイクルに入れた強者(つわもの)ですね」

「植物が増え始めると、それをエサにする害虫を含む生き物たちもまた入り込んできます。そういった場所では、その植物をエサにする新たな害虫が突如登場することがあります」
「焼けた木材や新しく生えた植物に集まる昆虫が増加し、そこにまだ天敵がいなければ一時的に害虫の数が爆発的に増加することもあります。そうこうしているうちにさらに新たな植物が育ち、これにより害虫の種類や数も変化します」
「新たに生えた植物が特定の害虫にとって良い餌場となり、それをエサにする天敵が現れ、ということを繰り返しながら次第に食物連鎖の一部が形作られ、生態系が出来上がってきます」
生態系の再生は「時間がかかる」
「とはいえ、これには時間がかかります」
「植物は長い時間をかけて、例えば鳥の糞や風に運ばれてくるコケやススキ、イタドリ、シダなどのやせた土地でも育ちやすい、コケや草、また地中で生き残った植物の種や根が芽生え、時間とともに成長が早く過酷な環境に強い松などの針葉樹が生え、最後にゆっくりでも様々な生物のエサや住処になりやすい広葉樹が生えてくる…というイメージです。その前に心配なのは火災にあった土壌がどうなるかというのもあります」