各地で老朽化した水道管が破損し、水が噴き出す事故が相次いでいる。こうした中、衛星とAIを駆使した新たな水道管の調査方法が各自治体で広がっている。
相次ぐ水道管漏水事故 衛星・AIでリスク検知

民家の屋根よりも高く上がった水柱。先月2月24日、埼玉県所沢市で老朽化した水道管に亀裂が入り、水が噴き出す事故が発生した。2月11日には、千葉県大網白里市で水道管から激しく水が噴き出し、翌日の12日にも大阪府堺市で水道管が破断し、道路に水があふれるなど全国で老朽化した水道管から水が噴き出したり漏水したりする事故が相次いでいる。
国内の水道管の総延長はおよそ73万kmで、日本水道協会によると、2022年度時点で全体の23.5%に相当する約17万kmが法定耐用年数である40年を超えている。水道管の老朽化により、漏水調査に迫られている自治体から続々と依頼を受けているサービスがある。

JAXA・宇宙航空研究開発機構も出資する、宇宙スタートアップ企業の「天地人」が提供する「宇宙水道局」。
天地人は、2019年から世界中の衛星から得られる気象情報や地形情報、地表面温度といった宇宙ビッグデータを分析。そのデータを使って、どの農作物がどの土地での栽培に適しているか、効率的な再生可能エネルギー設備の設置場所の選定といったサポートを行っている。
その宇宙ビッグデータから得られる地表面温度などに、自治体が保有する水道管の材質や使用年数、過去の漏水の記録などのデータを掛け合わせ、天地人独自のAIで水道管の漏水リスクを評価するのが「宇宙水道局」。
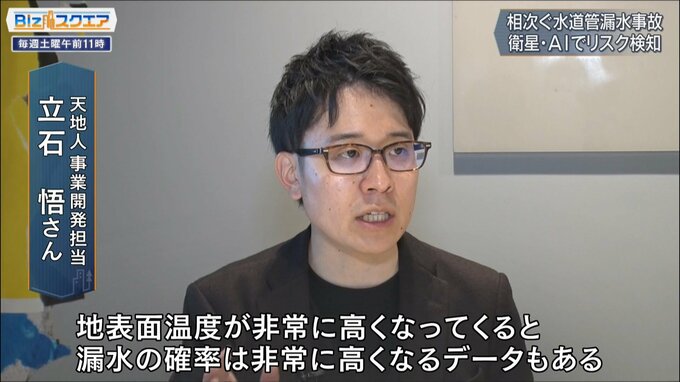
天地人 事業開発担当 立石悟さん:
地表面温度が非常に高くなってくると、そこでの漏水の確率は非常に高くなってくるというようなデータも出てきている。あとは(昼夜の)温度差。温度差が非常に高くなるところは漏水の頻度が高いという結果なども出ている。

宇宙水道局は、地図上で100m四方をメッシュにわけ、漏水リスクを5段階で表示。自治体はこのリスクマップを基に、優先順位をつけて効率的に調査を行う。
サービス開始前に愛知県豊田市で行われた実証実験では、宇宙水道局が漏水リスクが高いと分析した249の区域のうち65区域で実際に漏水が発生していて、その有効性が評価された。去年2024年、当時の岸田総理大臣がこのサービスを視察するなど政府もデジタル技術を活用した水道管管理に注目している。
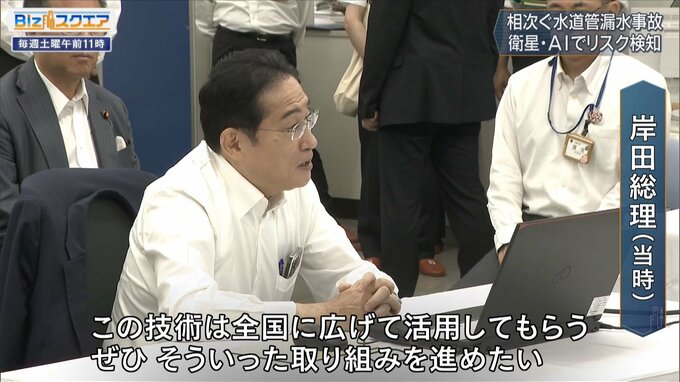
岸田総理大臣(当時):
この技術は全国に広げて活用してもらう。是非そういった取り組みを進めたい。














