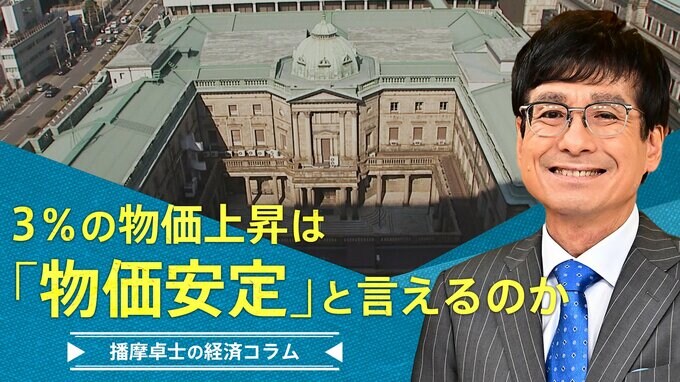10月に入り、続々と商品の値上げが押し寄せています。帝国データバンクの調べでは、食品主要105社の10月の値上げ品目は6532品目と、8月や9月の2000品目余を大きく上回っており、消費者物価をさらに押し上げることになりそうです。8月の消費者物価指数(除く生鮮食品)は、前年同月比で2.8%の上昇と31年ぶりの大幅な上昇でした。生鮮食品を入れた総合指数では、すでに3.0%上昇を記録しており、この分だと、インフレの基準指標である、生鮮食品を除く消費者物価指数も、まもなく3%台に乗せそうです。
■1991年の物価上昇は全く違う光景
31年前の1991年の消費者物価指数(総合)は、3.3%上昇でした。1991年と言えば、「バブル経済」のピークは越えたものの、多くの人々はまだバブル崩壊を認識せず、サービス価格を含めた幅広い品目が上昇していました。賃金も上昇しており、現金給与総額(月間)は前年比で4.8%も上昇しています。つまり、3%インフレでも実質賃金は1%以上も上がっていた計算になります。一方、7日に発表された今年8月の実質賃金は、1.7%ものマイナスでした。実質賃金のマイナスは4月以降、5か月連続で、賃金が物価上昇に全く追いついていません。同じ程度の物価上昇でも、懐具合の「耐性」は、31年前とは全く違うのです。
■3%の物価上昇は日銀の目標の1.5倍
政府・日銀の物価目標は2%です。実際に3%の物価上昇となれば、目標の1.5倍です。物価上昇への耐性が極めて低い時代にあって、目標の1.5倍もの物価上昇は、物価が安定した状況とは、とても言えないように思います。言うまでもなく、中央銀行である日銀の使命は「物価安定」であり、そのことは日銀法にもしっかりと書かれています。にもかかわらず、目標の1.5倍にも達した物価が安定しない状況に対して、何ら行動していません。むしろ日銀は、現在の物価上昇は一時的なコストプッシュによるものであり、来年には再び1%台に戻るという見通しを示し、「何もしない」ことを正当化しています。
「何もしない」で待っていれば、良いことが起きるのかと言えば、「賃金の上昇を伴った望ましい物価上昇が実現するめどは立っていない」と、黒田総裁も認めています。緩和継続こそが、前向きな循環に向けた唯一の解、というのが日銀の理屈なのでしょうが、ただ「何もしない」で待っているだけ、と突っ込みたくなります。
■黒田総裁。退任後の政策維持にまで言及
さらに黒田総裁は、先日の記者会見で「今の政策を、当面変えるつもりはない」と明言した上で、「当面とは数か月ではなく、2,3年」とまで踏み込みました。自らの任期を超えたはるか先までの政策継続を宣言する「越権」ぶりで、この日の円安を勢いづかせ、24年ぶりの円買い市場介入のきっかけを作ったのでした。これでは、「異次元緩和という今の政策の堅持」が自己目的化しているようにさえ見えます。
かつて名議長と評されたアメリカの中央銀行にあたるFRBのグリーンスパン元議長は、「物価が安定した状態とは、家計や企業が物価の変動を気にかけずに済む状態」と定義しました。物価上昇への耐性が低い日本では、今やほとんどの経済主体が毎日、物価の変動を気にしています。すでに物価は安定していないのです。「中央銀行が物価安定を軽んじている」と、国民が感じるようになれば、中央銀行への信頼が失われかねません。
播摩 卓士(BS-TBS「Bizスクエア」メインキャスター)