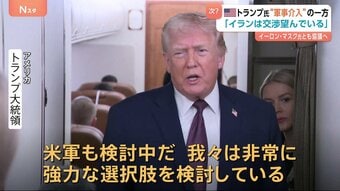発動には「時間」と「ばらつき」も
ウォールストリートジャーナル紙は、今回の「相互関税」の法的根拠は現時点で明確ではなく、既存の複数の法律が適用されるのではないかと報じています。要は、「見切り発車」丸出しの「何でもあり」です。都合よく決められるという、実に「身勝手な」話です。
こうして見ると、国別の調査期間や、その内容には相当ばらつきが出そうです。発動は、調査後すぐという国もあれば、交渉による猶予が認められる国も出るでしょう。
一律関税ではなかったこと、即時発動でもなかったことから、13日のアメリカの株式市場はむしろ好感して値上がりしたほどです。市場は実体経済に影響を及ぼすのはまだ先の話と見ているのでしょう。
首脳会談で何も知らされなかったのか
一方、わずか1週間前にトランプ大統領と首脳会談を行った石破総理は、会談の成功ぶりをアピールしましたが、先に発表された鉄鋼・アルミに対する追加関税も除外されず、今回の「相互関税」では、国として名指しさえされる有り様です。トランプ氏から事前の通告も相談もない「同盟」の、どこが「新たな高み」なのか、私にはさっぱりわかりません。
過去の日米首脳会談では恒例だった、首脳2人だけの「サシ」の会談も、今回の石破・トランプ会談では実現しなかったのですから、機微に触れる話などできなかったのでしょう。「失敗」「失態」がなかっただけの話で、すべてはこれからの交渉次第と考えるべきです。
考えてみれば、先進国と発展段階の異なる途上国の関税が、同じでなければならないといったルールなど、聞いたことがありません。途上国に産業育成のために一定の時間を与える一方、先進国が市場を開くことで経済発展を促して、段階的に関税を引き下げて行くというのが、アメリカが主導してきた戦後の通商秩序でした。
そのアメリカの大統領が、「堂々と」、「相互的」などと、法的根拠もないままに居直る世界に、私たちは生きています。
播摩 卓士(BS-TBS「Bizスクエア」メインキャスター)