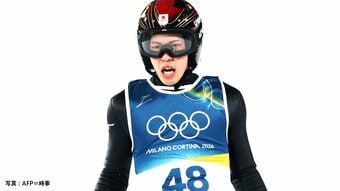――齊藤さんは、一緒に撮影する部隊の中に入られていたんですか
齊藤 施設にはテレビもあるので、ちょっと職業的に(俳優としての)僕は作品にとって「ノイズ」になりかねないという事は当初から思っていたので、僕は主に施設の職員の方たち、大人たちと、どういう作品にしていくか、いつぐらいにどういう形で世に出すか、どういう部分をケアしながら、アウトプットしていくか、というような事を説明に行く、そういう役割でした。
――こういった施設を撮影するのは、ハードルが高い上に、撮影される子どもたちへの向き合い方も難しいと思いますが、どのように撮影を進めたのでしょうか
竹林 子ども自身の意思を第一に、インタビューさせてくれる子どもたちから、話を聞いていきました。最初は、撮影に興味を持っている子どもが、どんどん近づいてきてくれた…という感じです。
竹林 撮影していると、子どもたちも、最終的にどういう映画になるのか、みんな気になっていて、「何とか、みんなにとって良い影響があるように…ということだけを、僕たちも願って作っているよ」という事を伝えながら、「何のために撮っているのか」という事を、必ず共有しながら、それを必ず守りながら、子どもたちとコミュニケーションしていました。

――「出演者のプライバシーを守る」という使命もあると思うが
齊藤 そうですね。そういう意味では僕らとしても、上映後も、ずっと被写体を守っていくという思いです。そのあたり、当初からお互い懸念しているものは一緒だと思います。ただ、僕が今回「大きな家」を企画するきっかけの一つが、施設にいる子どもたちが、何か公のものになるときに、必ず目線が入ったりモザイクが入ったりすることへの違和感なんです。
齊藤 もちろんそれは、彼ら彼女たちを「守るため」でもあるんですが、ある時に職員の方から「同時に、それを見た子どもたちが、みんながみんな、『守ってもらっている』と思うわけではなく、『自分は自分の存在を ぼかされる存在なんだ』と思っている子も、中にはいるんです」と伺ったんです。
齊藤 だから映画になるということに、(プライバシーに対する懸念だけでなく)すごく前向きな意見も多かったですし、実際、劇中の子どもたちもすごく輝いてて、「知ってほしい」、「観てほしい」という子どもたちの思いが、みんながみんな、そうではないですけれど、今回の作品の「光」となってくれていたので、これは必然だったのかもしれないと 今は思っています。