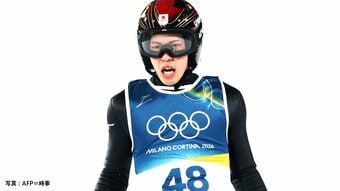――映画のみの公開で、DVD化等をしない…となると、プロデューサーとしては、興行収入的な問題もあると思うが
齊藤 そうですね、数ある作品の中で こういう作品があってもいいんじゃないかな…と。「14歳の栞」という作品があったからこそ生まれた作品ではあるんですが、なんていうんですかね…作り手の「純度」みたいな…「思いやり」が詰まった作品。
齊藤 「思いやり」って、やっぱりアウトプットの時に 映画だとすごく出るんですよね。ただただ公開して終わり…じゃなくて、「手渡し」のように、時間が経っても、賞味期限を設けずに「手渡し」のように届けていく映画って、実はたくさんあるんですよ。フィクション・ノンフィクション問わず… この作品は、「手渡し」のように届けていく。その分、劇場さんと観客の方に協力してもらって、一緒にシェルターになって、この映画を育てていく守っていく、より参加型の劇場映画。
齊藤 この配信全盛の時代に「情報のシェルター」になるのが、実は映画館なんだ…。というふうに新たな劇場の意味合いも含めて、この作品がまだ見ぬ作品の、一つの目印になったら良いなと思っています。

齊藤 やっぱり僕自身も最初、児童養護施設という存在に対して、情報で外枠だけを固めて、そういう場所があって、そういう施設で生活している子どもたちがいる。…で次に行っちゃっていたんですよ。一歩踏み込まず…。
齊藤 ただ、一歩踏み込んでみて、こういった形で彼らと接してみて、僕らが思う「普通」と、施設の中で思う「普通」というものの“差”を感じましたし、何かその漠然とした「普通」というものが、この作品を通じて「重なっていく部分がある」ということが、この作品に教えられる一番のことだなと思っています。バイアスや圧力みたいなものが無い純度で作ったものなんですね。
齊藤 だから本当に…塩加減としては非常に味付けが濃いものではないので、映画館で ただただ「自分の普通」と、「観ている人の普通」と、この「大きな家の中の普通」というものが、合わさって、自分の物語になっていってくれたら、彼ら彼女たちが、喜ぶんじゃないかな…と思います。
齊藤 あと、年代別に描かれている形になっているんですけど、ここは1人の人格の成長譚のように思えたんですよね。だから、もちろん個人差はあるけど、年代によって、施設にいた時間によって、その施設への思い… 他人なのか、家族なのか、その間なのか、っていうことが どんどんグラデーションになっていくような感覚を受けたので、そんな(自分の中でいま考えている)「こうだろう」という施設での「当たり前の日常」みたいなものを、ぜひ映画館で体験していただけたら、作った甲斐があるのかなと思っています。

【担当:芸能情報ステーション】