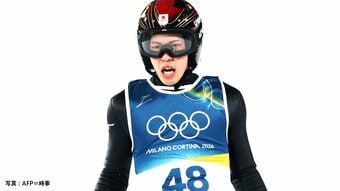――「被写体ファースト」という点が、監督の作品らしいなと思ったんですが、齊藤さんは そういった所も含めて、竹林監督にお願いしたい という事だったのでしょうか
齊藤 そうですね、僕もかつて監督の「被写体」だったこともありまして、マダガスカルとかパラグアイとか、カンボジアを一緒に巡った仲なんですけど、竹林監督は、その時もですが、今回も、カメラを回していない時に意味を持つ監督さんで、何度も何度も施設にカメラを持たずに訪れて、自分たちも自分のことを話す、というような…
齊藤 下手したら、カメラって凶器にもなりうるもので、(竹林監督は)そういうスタンスではなく、被写体を第一にして、丁寧に撮影を進めていく方です。子どもたちって すごくビビッドなので、大人の思惑とかにすごく敏感なんですよね。だけど、監督のご覧のような心根というか、優しさ、寄り添い方というものに、子どもたちが だんだん自分の言葉で、自分の物語を、自ら話してくれるようになった。施設との出会いから数えると、3年…足かけ4年ぐらいの制作期間ではありました。
齊藤 かかるべくしてかかった時間ではあるんですけど、竹林さんのチームじゃなかったら、多分撮れなかった心が、たくさん詰まっている作品になったな、と思っています。
――カメラで撮影を始めたのは、どのくらい経ってからですか
竹林 そうですね…齊藤さんが施設の方々と元々お付き合いがあって、行かれていて、齊藤さんに誘っていただいてから1年ぐらいは一緒に… ハロウィンのタイミングとかに ちょっと行ったりとかしながら、お話を聞く… そして、みんなに「いつか、みんなが主人公の映画を撮りたいんだよね」みたいな話をして、顔を覚えてもらって…
竹林 それで1年ぐらい経ってから、ゆっくり徐々に1ヶ月に2、3日撮影に行く… っていうのを半年ぐらい続けて、その後、月の半分ぐらいは行かせてもらう… というのを半年ぐらい続けて… という感じで、撮影の濃度もグラデーションがありました。
齊藤 機材とか、幼い子もいたので、みんな興味を持って、録音機材やカメラを、子どもたちがいじって撮影したり、壊れる直前ぐらいまで(笑)興味を持っていました。やっぱりカメラが入ることで、日常生活に違和感は、当然みなさん感じていらっしゃって… 職員の方たちも そうなんですが、それが徐々に馴染んできた頃に、いろんな対話を監督が始めてくださったのかなと… そんなグラデーションでした。

――カメラはどのくらいの大きさだった
竹林 カメラは結構大きくて、映画用のカメラを使っていて、すごく綺麗に撮れてデータもめちゃくちゃ重いんですけど、マイクも、大きいマイクを持っていたので、子どもたちからすると、相当、違和感があったと思います。
竹林 撮影が進むにつれて、だんだん機材の操作なども覚えて、録画のレックボタンを(ふざけて)消してきたりとか、知らない間に自分たちで撮影して、素材を撮ってくれたりとか、みんなすごい機材を使えるようになっていたのが面白かったです。
齊藤 職業体験的なことも、結果的に振り返るとあって、「映像の世界」に興味を持った子どもたちも何人かいました。実際にその先の進路とかを監督に相談したりする子とか、監督に自分で書いた脚本を読んでもらったりする子とかもいました。
齊藤 今回、映画の撮影部隊といっても4人からMAXでも6人なんですけど、子どもたちにとっては「働く大人たちと接していた期間」でもあって、カメラの前に立つだけじゃなくて、「映像を作る職業」って、どういうものなんだろう?いうことを考えるきっかけになって、彼らの未来に、実は既にすごく影響がある作品なのかな?というふうにも思っています。