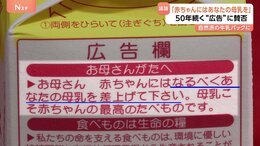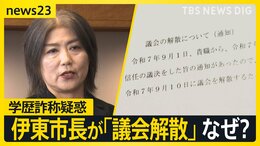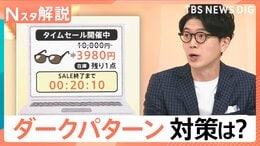■2022年受賞研究は…「つまみを回す指の使い方」
では、一体どういう研究だったのかを見ていきましょう。
ドアノブなど円柱のものを回す際に、大きさや形状によって、私たちは無意識に指の使い方を変えているのです。その「無意識の行為」を統計的に明らかにしました。
どうやって明らかにしたのか、実験を行っています。
実験方法は、45本の直径が異なる円柱を被験者32人にひたすら回してもらい、指の使用本数や位置を分析したそうです。
井上キャスターの目の前に様々な円柱形のキャップなどをご用意いたしました。蓋の直径1.2センチのゼリー飲料、そしてペットボトルは蓋の直径3センチ、ウェットティッシュは蓋の直径10.5センチです。
それぞれ何本の指を使うか、ゼリー飲料からやっていただきましょうか?

井上貴博キャスター:
意識したら駄目ですね。直径1.2センチのゼリー飲料のつまみは、指2本でつまみました。ペットボトルの直径3センチのつまみも、私2本です。ウェットティッシュのボトルは2本ではいかないよね。指5本使います。
ホランキャスター:
このような45本の直径が異なる円柱を皆さんに回してもらった結果、皆さんは主に指を何本、使いますかというものです。
▼直径1センチ未満は2本(親指と人差し指)です。先ほどのゼリー飲料のつまみが含まれる▼直径1.1センチを超えるつまみは、3本使われた方が多かったそうです。▼直径2.6センチを超えるペットボトルのつまみなどは指4本。先ほどのウェットティッシュのボトルなどの▼直径9センチ以上は、5本という結果でした。

試してみますと、意外と結果と違う方も出てくるということで、いかにこれを実験として統計的に捉えるということが意味があったものなのかはわかりますよね。
井上キャスター:
手の大きさや指の長さがあるかもしれません。
ホランキャスター:
松崎教授は「この結果は、つまみの大きさや形状をデザインする際に役立つと思います」と話されていました。
井上キャスター:
現代社会でこれだけ情報があふれている時代に、生活の中に当たり前にある行動に着眼する点は、素晴らしいなと思うし、日本人として誇らしいなと感じました。
東京都立大学 佐藤信 准教授:
イグノーベル賞ではありますが、正直「Ig」ではないとまず思いました。実際、プロダクトデザインにも使われているということですし、研究として特徴的なところにいかにオリジナルのアイディアを出せるかはすごく大事なので、みんなが当然使ってるものをちゃんと学問的に捉えられるのは、すごい能力だと思うんですよね。
私自身も政治学がメインですが、結婚活動の歴史をやっていて、時々冷ややかな目線で見られることがあるんですけど、いずれ私も評価されたらいいなと思いました。
井上キャスター:
ノーベル賞ももちろん素晴らしいですけれど、イグノーベル賞の方が身近なので、感覚としてわかるところが多いと考えると、どんどんイグノーベル賞自体の権威が上がってるのではとすら感じます。
東京都立大学 佐藤信准教授:
あと面白かったのは、今回他に受賞している研究は、ここ1、2年前に英語で書かれたものなんですね。今回受賞した松崎先生たちの研究は、20年前に日本語で書かれている研究なんですよ。創設者のマーク・エイブラハムズ氏は、日本語の論文でも今読むのは簡単なんだというようなことを言ってるんです。つまり、おそらく機械翻訳みたいなものが進展してきて、インターネットで色々なものを公開するようになってくると、これまでは日本語で書かれたものはガラパゴスだと見られていましたが、もしかしたら、こういった日本の学知みたいなものが今後、再発見や再評価されることもあるのかなとも思いましたね。