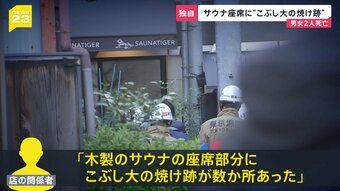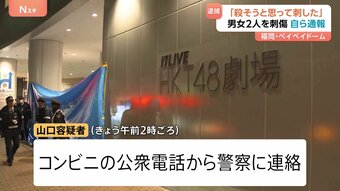“水素のまち”が目指すのは

水や化石燃料、廃プラスチックなど、あらゆる資源から作ることができる「水素」。
ホテル業界をはじめ世界が注目する中、福島県に“水素のまち”も誕生しています。
人口2200人ほどの町には約80台の「水素カー」が走り、子どもが通学に使うスクールバスも「水素バス」。温浴施設のエネルギーの一部にも水素が使われています。

ここは、福島県の沿岸部にある浪江町。“水素のまち”と言われる最大の理由は世界最大級の水素製造施設『NEDO』があるからです。
この施設では水を電気分解して大量の水素を作っていますが、その時に使う電気は太陽光を使った自然エネルギーで発電。

『NEDO』水素アンモニア部 大平英二さん:
「太陽光発電のパネルが6万8000枚あって、全体の面積では東京ドーム4個分ぐらいの大きさ」
こうして作られた水素は全国に送られ、東京を走る水素バスなどにも使われていますが、浪江町が水素エネルギーに力を入れる理由のひとつは「復興」です。

福島第一原発から約10kmの浪江町は、人口が10分の1まで減少。震災から13年経った今でも75%が帰宅困難区域です。
浪江町役場 新エネルギー推進係 渡邉元気さん:
「完全に復興が終わったというのは全くなくてまだ道半ばというのが現実。水素を活用した町おこしにもチャレンジしていきたいし、未来の子供たちが水素を当たり前に使っていけるような、そんな社会にしていきたい」
水素エネ普及への2つの課題

水素の活用が広がる一方で、普及への課題も残されています。
1つは価格。水素を作る過程では電力が必要なので製造コストがかかり、プロパンガスの約3倍の値段になってしまいます。
もう1つは安全性。水素は可燃性の気体なので、安全に輸送や貯蔵ができるインフラの整備が必要です。
まだまだ課題のある水素ですが、アメリカの地質研究所によると、全世界の地中に埋蔵されている量は5兆トン!これは1万年以上の資源になるとのことで、水素の可能性に多くの注目が注がれています。
(THE TIME,2024年11月7日放送より)