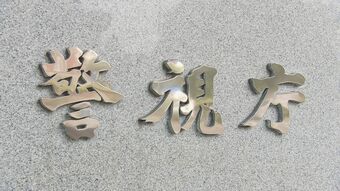投票のサポートは、一人ひとりの障害の度合いや特性に配慮して
2013年までは、重い障害があって、後見人がついている人に選挙権はありませんでした。納得がいかない当事者と家族が訴え、最高裁の違憲判決が出て、投票できるようになったのです。
それ以後、「わいわいてい」の中では、投票のサポートについて、様々議論していたところに、2016年、「津久井やまゆり園」の事件が起きました。
「わいわいてい」を運営するNPO「もやい」の山崎幸子さんは、事件の犯人の「意思疎通ができない人は、要らない」という言葉から、障害者の意思の表現をどうサポートするか、より考えさせられたと言います。
NPO「もやい」の山崎幸子さん
「毎日のことで、自分自身の意思をきちんと持ってるはずなのに、その意思をまず表現する手立てが、私達は普段からできているかどうか。選挙も選んでいくことの一つで、選挙のサポートを考えていく中で、私達も選挙について、考えなくちゃいけなくなった。わかりやすい言葉で伝えるっていうことが一番大事で、でもそれは、私達もわかりやすく選挙を理解していくことに、つながっていきました」
「わいわいてい」で暮らす5人の入居者の障害の度合いや特性は様々です。
文字が書けない人は、投票所の職員に意思を伝え、代わりに書いてもらう「代理投票」という制度を使います。
一人の入居者は、選挙公報を利用した、スタッフ手作りの候補者一覧の紙を持って行き、それを、指でさして意思を伝えます。投票所の職員がそれを受けて、代わりに投票用紙に書きます。
品川区では、今回から、郵送される入場整理券と一緒に、「支援カード」が入っていました。何らかの投票のサポートが必要な人が記入するものですが、これまでは、投票所で渡されていました。「支援カード」が事前に郵送されることで、サポートしてほしいことをゆっくり考え、事前に書いておくことができるようになったのです。
この入居者が持っていくカードには「指をさして意思を伝える」以外に「ゆっくり説明してください」といったことも書いてありました。
「わいわいてい」のスタッフが期日前投票所まで付き添いますが、投票所の中には入れません。支援カードを投票所の職員に渡し、サポートを委ねます。
しっかり投票できたようで、終わった後、崎山記者が聞くと「選挙に行きました!」と力のこもった声で繰り返しました。

この他の「わいわいてい」の入居者3人も、それぞれがやりやすい状況の下、それぞれの方法で投票しました。
ただ、最高裁の裁判官の国民審査は、一人を選ぶのではなく、ふさわしくないと考えた人に×印をつけます。スタッフが、事前に制度の意味や方法を説明しましたが、投票とやり方が違うので、5人がうまく自分の意思を表せたかは難しかったかもしれません。
「わいわいてい」では5年前から、実際の投票のサポートに取り組んでいますが、山崎さんは「選挙は彼らの生活を良くしてくれる人を選ぶためのものです。この候補者はこういう人だ。別の候補者はこういう人だということを伝えられているかどうかも課題です」としながらも、「本当に、言葉が皆さん多くなりましたね。それは聞かれることが多くなったんだと思うんです。これがいい?こっち好き?こっちどう?といったふうに、普段から聞いている中で、言葉が多くなってきました」と話していました。
投票のサポートに地域差がある現状
サポートが必要な障害者や高齢者への対応は、自治体ごとに異なります。投票所側の対応も少しずつ改善されていますが、品川区内の知的障害のある人の親のグループは、例えば、当事者が投票に慣れるため、「模擬投票」を普段から実施するよう要望し続けています。
今回の取材を通じて、あらためて選挙について、そして、日常生活の中で、自分で決める、選ぶ、とはどういうことか、誰もが考えることにつながると感じた崎山記者でした。
TBSラジオ「人権TODAY」担当: 崎山敏也記者