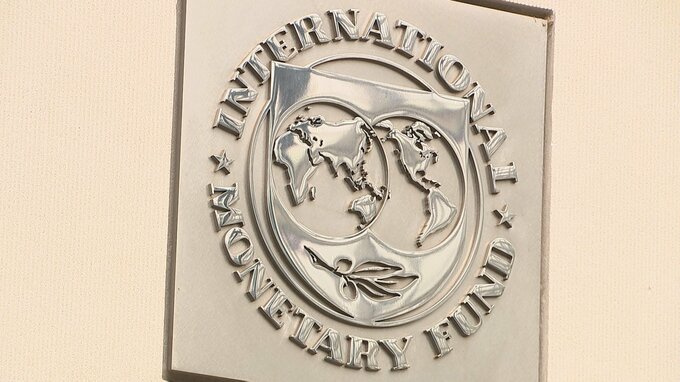IMFはインフレの後退を指摘し、OECDとIMFはそろってディスインフレをテーマとした
IMFのゲオルギエバ専務理事は17日、IMF・世界銀行年次総会に先立ち、演説を行った。ゲオルギエバ氏は「世界的なインフレの大きな波は後退している」と、インフレ懸念が弱まったことを良いニュースとして挙げた(筆者訳。以下同)。一方、「私たちの予測では、低成長と高債務という容赦ない組み合わせが待ち受けている。困難な未来だ」と、新たな課題を指摘した。
今後はディスインフレの局面が訪れるという見通しは、OECDも9月の世界経済見通しで指摘していた 。むろん、OECDやIMFの見通しがいつも当たるわけではないが、世界経済のテーマがインフレ対応から成長確保へシフトしていることは事実だろう。FRBは9月から利下げサイクルに入り、ECBも10月に連続利下げを決めた。
後述するように、今後の世界経済の課題が「低成長と高債務」だとすると、各国のポリシーミックスは金融緩和への依存度を高めることになると、筆者はみている。ゲオルギエバ氏は「改革」に焦点を当てることで労働生産性を挙げたり、イノベーションを起こしたりすることの必要性を指摘したが、これはIMF専務理事の立場からの「綺麗事」である。現実的には、これまでのように各国は金融緩和というカンフル剤に頼っていく可能性が高い。
インフレ鈍化は良いニュースだが、物価の水準は高いため消費は低迷へ
ゲオルギエバ氏はインフレ鈍化を良いニュースとしたものの、「インフレ率は低下しているかもしれないが、私たちが財布で実感する物価水準の高止まりは今後も続くだろう。家庭は苦境にあり、人々は怒っている」とした。これは日本でも確認される動きである。インフレ高進によって実質賃金が目減りする傾向はかなり収まってきたものの、個人消費は低迷したままである。これは、過去2年間で実質賃金の水準が5%程度低下したことが背景だろう。中央銀行はインフレ率を重視するが、人々が新たな物価水準に慣れるのには時間がかかる。ゲオルギエバ氏が指摘するように、インフレが収まったとしても、しばらくは景気が低迷することを予想せざるを得ない。IMFは世界経済の成長率が緩やかに減速していくと予想している。