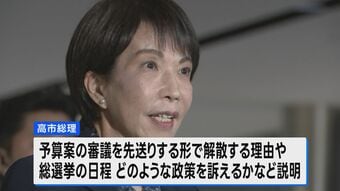担い手不足と高齢化…減り続ける保護司 解決の一手は?
大津市の事件の後、法務省が行った調査では、全国の保護司の約2割が「不安を感じている」と回答。
また、一部の対象者について、育成歴や性格などの情報が「事前に得られていない」という不満の声が上がりました。
法務省はこうした不安や不満を解消するため、3か月を目安に、心理学などの専門性を備えた保護観察官が直接、保護観察を行う取り組みを今年9月から試験的に始めました。
東京保護観察所 箕浦聡 首席保護観察官
「3か月間のアセスメントに基づきまして、再犯のリスクですとかそういったものが可視化されますので、保護司さんたちの不安の解消に繋がるものと考えております」
しかし、課題は安全対策だけではありません。

保護司の数はこの10年で1000人以上減少。高齢化も進み、今後10年で4割が退任します。
こうした課題を克服しようと、全国のモデルとなる取り組みが東京・荒川区で行われています。
小原実さん(63)は荒川区の職員として勤務しながら、これまでに7人の保護観察を担当してきた保護司です。

荒川区・日暮里区民事務所 小原実所長
「当時、保護司の担い手不足を聞いた区長が私達に声をかけていただいたのがきっかけです」
現在も小原さんを含む4人の職員が保護司として活動していて、区では仕事と保護司の活動が両立できるようサポートしています。対象者にとってもメリットがあります。

小原さん
「対象者の住宅問題や仕事、就労のことも含めて行政の守備範囲が広いので、仕事上のいろんな人脈を生かしながら適切な支援に結びつけることができる」
転換期を迎えている保護司制度。十島さんたちが描く理想の社会とは。
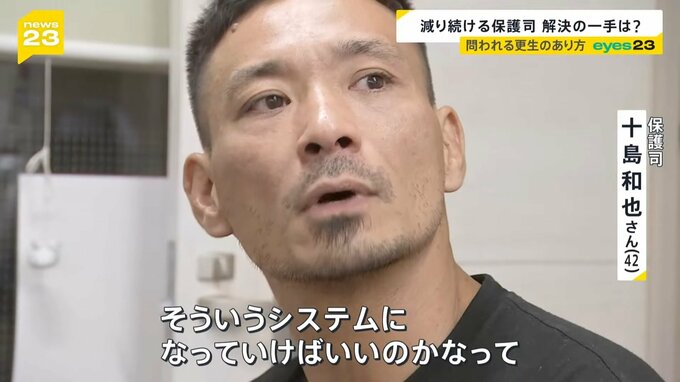
十島さん
「保護司がやらなくてはいけないではなくて、社会が全部受け入れられるようなシステムになっていけばいいのかなと」