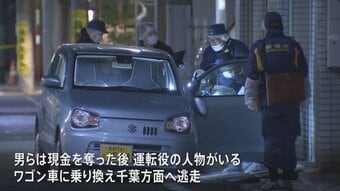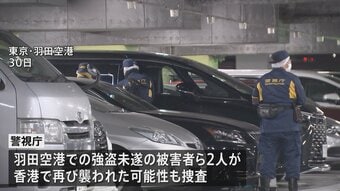値上げの常態化
最近の物価上昇は、単に原材料高を受けたものではなくなっている。エネルギーコストや人件費の上昇に押されて、たとえ原材料高のペースが鈍化しても、価格引き上げが続くようになっている。この現象は、食料品に限らず、製品全体に言えることだ。
中小企業庁が価格転嫁の状況を調べたアンケートでは、費用の内訳でみてどのくらいの価格転嫁率なのかを数値化している(データは食料品以外も含む全般の価格転嫁率)。そこでは、2023年3月→2023年9月→2024年3月にかけての変化が、次のように推移している。
(1)原材料の価格転嫁率 48.2%→45.4%→47.4%
(2)エネルギーコストの価格転嫁率 35.0%→33.6%→40.4%
(3)人件費(労務費)の価格転嫁率 37.4%→36.7%→40.0%
ここからわかるのは、最近はエネルギーコストと人件費のコストを転嫁する動きが進んでいることだ。この変化は、食料品の値上げがほとんどの品目に及ぶようになった背景とも重なる。注意したいのは、エネルギーコストと人件費のコストがともにまだ、価格転嫁率が低い点だ。今後も、これらの価格転嫁は継続していきそうだ。ここからは、値上げが常態化しつつあることを感じさせるものだ。
最後に、私たちはどのように食料品高騰に対処していけばよいのだろうか。食料品の中で節約ができないのならば、それ以外の支出を切り詰めるしかないということになる。
敢えて、食料費の中だけでのやりくりを考えると、次のような対処法も考えられる。
(1)自分で冷凍食品をつくる。生鮮食品は、価格変動が大きいので、どこかのタイミングで割安な時期が到来する。そこで購入したものを冷凍して取り置きする。これは生鮮食品でも可能である。例えば、主食のところで相対的に割安だと指摘したもちは、冷凍しておいて、朝食などに用いることができる。これも1つの節約術になる。
(2)ご飯を中心の食事。米の値段だけをみれば、先のデータでも20.5%と高騰している。しかし、つぶさに調べると、炊いたご飯と一緒に食べるお総菜には、値上がり幅の小さいものが多くある。梅干し(4.3%)、キムチ(5.2%)、納豆(6.0%)である。一頃よりも高くなったとはいえ、和の食材は相対的に輸入割合が低いので、食費を抑えられる。
(3)探索範囲を広げる。食料品の価格が店舗によって異なることは結構多い。時々、いつもの店舗以外の場所で購入する習慣をつけると、店舗ごとの価格差に敏感になれる。安いものを選ぶためには、自分の価格センスを磨くという点にも注意を払っておく方がよい。センスが磨かれると、ちらっと値札を見ただけで、「この商品は安い」と気付くことができる。
これらの3つの方法は、節約アドバイザーなどがよく指摘しているものでもある。参考までを掲示してみた。
(※情報提供、記事執筆:第一生命経済研究所 経済調査部 首席エコノミスト 熊野英生)