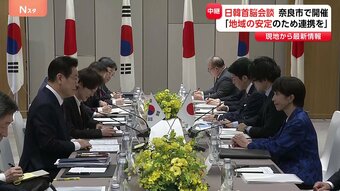■ワクチンヘジタンシーにとって最強のキーマン”となるのは?
ーSNSなど、様々な情報が錯綜している現代で、勝田医師が一番重視していることは何でしょうか?
勝田医師:
我々医師が、自信をもってワクチンを勧める体制をつくることだと思っています。様々なシチュエーションで「かかりつけ医とよく相談して決めてください」という言葉を耳にする機会があります。実際、かかりつけ医の先生の意見が、患者さんたちのワクチンに関する選択に大きな影響を与えることが知られています。
一方で、実は医療従事者の一部も一定程度のへジタンシーを持っています。例えば厚生労働省、小児科学会などが、より明確なメッセージを出してくれると、かかりつけ医の先生たちも、より自信を持ってワクチン接種を患者さんたちに勧めることができます。
小児科学会が小児に対する新型コロナワクチン接種が国内で導入された直後に公開した方針には「明確に推奨します」ではなく、「接種する意義があります」という表現を用いました。この判断は、新型コロナワクチンを小児に使用した場合の安全性有効性に関する情報が十分得られていなかった当時の判断としては止むを得ないものであったとも言えますが、現場を預かる小児科医が患者さんたちに積極的に接種を推奨するには、やや弱いメッセージであったかも知れません。実際に特に5-11歳における新型コロナワクチン接種率は明らかに低迷しています。(その後、日本小児科学会は、追加された多くの医学情報を根拠に、8月10日には「意義がある」から「推奨する」という表現に変更しました)
患者さんに最終的に説明をするかかりつけの先生たちは最強のインフルエンサーです。厚生労働省や学会からの情報提供は、単なる医療従事者への最新情報を提供するだけでなく、彼らに自分たちの推奨に明確な「お墨付き」を提供するという点で非常に重要です。実際、最近は厚生労働省だけでなく多くのアカデミアが多くの情報をホームページ等で「指針」などの形で様々な情報を公開しており、我々はそれらを拠り所にして患者さんたちに自信を持って説明をしています。例えば、そのような情報にバックアップを受けたかかりつけ医から患者さんに対して明確に「私は絶対に打った方がいいと思いますよ」と言われたら、多くの人が安心して接種してくれると思います。
あとはちょっと時間がかかりますけど、学校教育でのワクチン啓発も重要です。学校でワクチンとはどういうものなのか、教えていく、ということです。単にワクチンを推奨するのではなく、なぜそれぞれのワクチンの接種がすすめられているのか?接種をした際のメリット・デメリットにはどのようなものがあるのか?などを保健体育の授業などで教えておくことは、将来ワクチンに対する多角的な判断をするための素地になると思います。
※1:2021年12月公開「親がCOVID-19ワクチンを躊躇する要因:日本における横断研究」(※山梨大学大学院総合研究部附属出生コホート研究センターと同大学院総合研究部医学域社会医学講座)