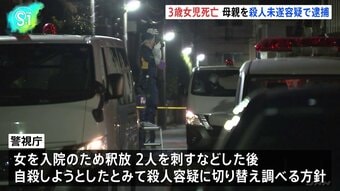◆メルカリ急成長の立役者が、なぜデジタル庁に?

今年4月にデジタル庁に加入した樫田光さん(38)は、元メルカリのデータアナリストで、データを分析するだけでなく、戦略におとしこみ、より良い「意思決定」をデザインするプロです。その能力を、デジタル庁でどう活かすのか聞きました。
***************
<データアナリスト 樫田光さん インタビューより一部抜粋>
Q:メルカリからデジタル庁に 不安などはなかったのか
あまり感じなかったですね。知り合いが何人かいたこともありますが、民間の人もスキルを活かしてきちんと活躍できていると聞いていたのでむしろ「チャンス」と捉えています。
Q:チャンスというのは?
これからの時代のインターネットとかスタートアップの世界というのは、既存産業の中で「重くてデジタル化が進まなかったもの」にどうアプローチしてどうデジタル化するか、という話で、すごく大変だけど、その代わりすごくリターンは大きい・・・という世界。そういう所だけが「手つかず」で残されている状況。だからこそ、デジタル庁の仕事が今後、重要になってくると思います。
Q:実現したいことは?
データ分析の専門職として採用されているので、その分野を大きく推進していきたいです。霞が関の省庁は民間のIT企業などと比べて、データをリアルタイムで見て、何か意思決定をしたりとか、みんなで数字をみて「いま何が足りない」「いま何をしなきゃいけない」という共通認識を作りながら進んでいくという文化は比較的弱いなと思っていて、当然データ分析の専門家がいないとか、データの扱いが難しいとか、コストパフォーマンスに合わないとか、周りが理解してくれないとか、いろんなハードルはあると思いますが、そこは結構時間をかけてでも乗り越えていきたいとは思っています。
Q:国民目線でいうと、データを活用することで何が可能になる?
2つの側面があると思っていて、例えば、デジタル庁の中で持っているデータを解析して、個人に対してデータを元にしたより良いサービスを届ける・・・という話と、もうひとつは、そもそも政府の中で「何をするか(政策決定)」だとか、「今この物事がうまくいっているか(政策検証)」とかを判断して決定する「具材」としてデータをちゃんと見るという話しで、私はまず後者に手をつけたいなと思っています。
Q:日本の政策決定をデータドリブンに?
はい。霞が関の中にたくさんあるデータが活用されていない、いまあるデータにどういう「力」があるのかというのを、まず省庁が理解する必要があると思っているので、なぜこの政策をしたのかとか、なぜ組織の改編をしたのかっていうのが、もう少し数字だったり、エビデンス・事実に基づいたものに変わっていくと、より良い政策運営ができるようになるし、説明責任をすごくシンプルな形でできるようになると思います。
Q:政策がぶれにくくなる?
そうです。いろんな意見がある中で、数字やデータをきちんと示して判断する「軸」がないと「私が思うには・・・」という話で終わってしまいます。なので、それをつなぐ「ツール」としてデータがあるのかなと思います。日本をデジタル化するというのは、すごく時間はかかるものだと思っています。どこかひとつを変えれば良いわけではなく、表から裏から全部一気にゴソっと変えないと、真の意味でデジタル化のメリットは得られづらいと思います。時間をかけてでも、そうした本質的な変化、進化によって結果を出していきたいです。
****************
「データ」というと、何か国民の個人情報をのぞかれるのではないか?とか、不安要素の方をこれまで指摘されることが多かったと思います。
今回、実際にデジタル庁でデータ分析や戦略の整理などを担当している樫田さんと話して感じたのは、政府と国民がしっかりとした信頼関係を築き、個人情報に配慮した上でポジティブにデータを活用することができれば、明るい「未来」を築けるかもしれない・・・ということでした。
テレビでは伝えきれなかった
デジタル庁における「デザイン」と「データ」の話。いかがだったでしょうか?
ちなみに、タイトルの元になった
「デジタルで、明日と5年後の『うれしい』をつくる」
という言葉は、
デジタル監の浅沼さんが以前「note」に書いた言葉です。
河野大臣がデジタル庁の担当となり、優先順位をつけた上で、従来よりも「うれしい」を早く国民に実感してもらえるよう、目標を前倒しする方針を表明しました。
現場には、相当な負荷がかかることになりますが、是非「働き方」の課題も乗り越えた上で、日本社会のDXを実現してほしいと感じました。
経済部 デジタル庁担当 池田誠