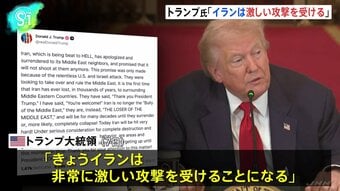切りつけられ、注射器で血を

自宅でのインタビューの翌日、我々はモニカがよくトレーニングをする地元のスタジアムで待ち合わせた。スタジアムには400メートルのトラックがあるが、うち300メートルは草が茂り、一部は水浸しだ。

到着したモニカ、上着を脱ぐと東京パラリンピックのTシャツが現れた。唯一使える100メートルの直線を行き来しながら、軽いジョギング、ストレッチなどを行う。本気では走らない。妊娠しているからだ。
予定日まで2か月ほど。お腹はしっかり出ている。相手の男性はまだ若く、経済的に自立していないためミリアムは結婚を許していない。“今結婚してもモニカが苦労するだけ”と。

この時はまだ東京パラリンピックは延期されていなかった。モニカに「間に合うの?」と聞くと「まずは無事に出産して、すぐにトレーニングに戻るつもりです。そうすれば十分間に合いますよ」と、“何の問題もありません”、的なトーン。
生まれてくる子供はパラリンピックを記憶するにはまだ幼過ぎるけど、モニカは「大きくなったら賞状やメダルを見せます。そうすれば母親がアスリートだったって信じるでしょう」と、そんな日が来るのを楽しみにしている様子だった。
モニカと、この日はアフロヘアにしてきたミリアムにスタジアムのスタンド席で話を聞く。前日のインタビューのあとの立ち話でモニカもかつて襲撃されたことがあると知り、そこを突っ込んで聞きたかった。以下はミリアムの話である。

事件が起きたのはモニカが4歳の時だった。当時、ミリアムはモニカの父親である前夫と、その親族と暮らしていた。
ある日、ミリアムが買い物に出かけ、帰ってくると、モニカの背中に傷がつけられ、血が出ていた。着せていた白い服も切り裂かれ、血が付いていた。親族に「誰が私の子にこんなことを」と問うと、父方のおばがこう言い放った。
「“私の子”って誰のこと?このアルビノのことかい?一族の恥さらしだよ」
幼いモニカは、おばを指してミリアムに訴えた。「この人にやられた。カミソリで切られた。注射器で私の血を吸い取ったんだ」と。ミリアムが問い詰めると、おばは「呪術用に、と依頼されたんだ」と認めた。
ミリアムは「この一族とは暮らせない」と見切りをつけ、モニカを連れて家を出たのだった。モニカの実の父がどこまで襲撃計画を知っていたのかは、今となってはわからない。ミリアムはその後再婚、自宅でのインタビューに同席していた2男1女をもうけた。
アルビノであるというだけで、血のつながった親族に自分の血を、身体を狙われる。酷い話だ。が、アルビノ襲撃において残念ながら親族の関与は珍しくはない。
ミリアムが話している間、モニカはずっと黙って聞いていた。当時のことは覚えていない。コトを認識したのは、大きくなってから背中の傷に気づいてミリアムに「この傷は何?」と聞き、教えられた時からだ。

(それを聞いて辛かったでしょう?)
「ええ・・・そうですね」
(でも、もう克服した?)
「はい。神様が愛して下さってますから」
今でも湧いてくる怒りと嫌悪を露わに生々しく語ったミリアムに比べ、モニカは言葉少なだった。
母娘の過ごしてきた21年という時間を想像する。襲撃事件をきっかけに壊れた家族。小学生のモニカ、中学生のモニカ、学校でもいろいろあっただろう。
でも彼女は陸上に目覚めて才能を開花させ、首都ルサカに、そして海外にも出て行って結果を残してきた。ミリアムはずっと支えてきた。「想像する」と言っては見たものの、その時間の濃さ、分厚さは、想像が追い付くようなものではない。
それでも、パラアスリートの一人一人が背負っているストーリー、特に障害者が厳しい生活を強いられることの多い国々から来るアスリートたちのストーリーを、少しでも想像してみたい、そう思った。