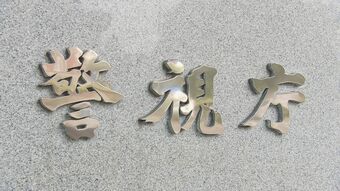子供の変化、そして課題
もう一人、平野和己さんが客席にいました。父親の平野泰史さんが登壇し、「以前は、こんなふうに30分以上、じっと座っているなんて全くできなかった。驚いている」と、最初に話しました。
和己さんは、事件の2年後、地域のグループホームに移りましたが、大声をあげたり、何かに強くこだわる、自他を傷つけたり、といった「行動障害」が出ることから、別の入所施設に移っています。
ただ、そこでは平日、やまゆり園では一切させてもらえなかったという仕事で作業所に通いながら、休日には、「行動援護」というサービスを受け、自分が行きたいところへの外出をしていて、今は落ち着きを取り戻しています。
再びグループホームに移ることを目指している和己さんが、ヘルパーと一緒に、バスに乗り、体育館でプールに入ったり、食事をしたり、おやつを買ったりと、楽しんでいる様子を動画で紹介しながら、父親の泰史さんは「本人が進んで外へ行くことは非常に大事だと思ってます。それによって、いろんな社会と接する。社会性が身につく。本人も活性化されて、いろんなことができるようになる」と、泰史さんの変化を語りました。
「ただ、実際は行動援護を簡単に利用できるかというと、なかなかできない。まず対応できる事業所はあるのですが非常に少ない。重度の子を見てくれる、それだけのスキルを持っているヘルパーさんがなかなか見つからない。その辺が問題になってると思います」と付け加えました。
元々の場所で3年前に、定員60人で再開した「津久井やまゆり園」でも2023年度から、入所者の意思を尊重して、5年間で、毎年12人ずつ地域に移るという目標を掲げています。
ただ、実際にグループホームに移った人は、これまでの1年あまりで3人にとどまっています。