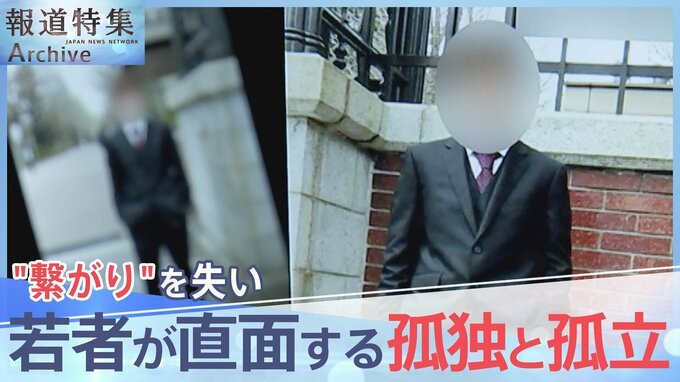核家族化が進み、兼ねてから日本社会の孤独・孤立化が深刻になっていると指摘されていましたが、この春から孤独・孤立対策推進法が施行され、政府もその対策を本格的に始めました。
特にコロナ禍で浮き彫りになったのが、高齢者だけでなく学校生活を送る若者が他人と直接的に関わる機会を失い、心身の不調を訴える姿でした。
(西村昭人)
新型コロナで対面授業が中止され「孤独感は一番辛かった」
4年前、都内の大学に通う21歳の男性を取材した。新型コロナで対面授業が中止されてから1年近くが経っていた。

大学生(21歳)
「他者とのコミュニケーションが全く取れない孤独感は一番辛かった。調べものをしたくても図書館が開いてなくてレポートに行き詰っても人にどういう状況か聞いたりできなかった」
体調に異変をきたしたきっかけは、オンライン授業での課題が溜まっていったことだった。プレッシャーから腹痛でトイレに籠ったり、夜眠れなくなることが続いた。
2か月が経った頃、男性は親に「大学を退学したい」と相談したが…。

大学生(21歳)
「卒業するのが厳しいと感じていて、大学を辞めようと思って親に伝えたら、『死ぬ気でやれば卒業くらいできるでしょ』とか理解してもらえなくて喧嘩したりした」
誰にも悩みを理解してもらえないという思いが募っていった。そして…
大学生(21歳)
「大学も卒業できないなんて、という思いから死にたくなっていた。実際クローゼットの中にネクタイで輪っかを作って首をかけたこともあったけど死にきれなかった」

そんな中、男性が辿り着いたのが医療法人財団が運営する若者向けの相談センターだった。ここでは精神科医らが地域の若者の相談に無料で応じている。
男性も眠れなくなったのを機に通いはじめ、大学の問題や親との関係性などについて相談するようになった。

相談員
「お母さんにうちに来てもらって状況を整理してもらったりしたけどどうだった?2人で話しても煮詰まっちゃってる状況だったと思うけど」
大学生(21歳)
「前は本当に顔も合わせたくないくらいだったんですけど。今は全然普通に話してますし。割と気を使われてますけどそれもちょっとうるさいなと思ったりするんですけどそういうのも思えるだけでも大分今は仲良くなれたのかなと思います」
男性は心療内科で適応障害と診断され、2年前、大学を退学した。