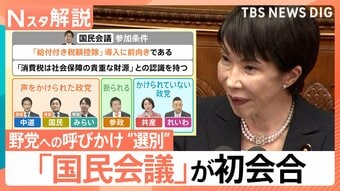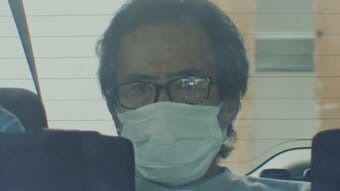競歩種目の変革期の影響も?
記録では世界記録(1時間16分36秒・鈴木雄介)、世界歴代3位(1時間16分51秒・池田)、世界歴代6位(1時間17分15秒・山西利和=28、愛知製鋼)を保持する日本が、世界でもナンバーワンと言っていい。
だが昨年から世界的に速いタイムが増え始めた。鈴木が世界記録を出した15年以降の、シーズン毎の1時間18分未満の人数は以下のように推移している。
15年:2人(日本選手1人)
16年:0人(1時間18分台3人。全員が日本選手)
17年:1人(日本選手0人)
18年:4人(日本選手3人)
19年:6人(日本選手5人)
20年:1人(日本選手1人)
21年:5人(日本選手1人)
22年:1人(日本選手0人)
23年:4人(日本選手0人)
24年:13人(日本選手5人)
競歩の場合、気象条件が好コンディションで、速いペースで展開した大会があれば、リスト上位の顔ぶれや好タイムの選手数が一気に変わってくる。それでも今季の、1時間18分未満選手数の増加は驚異的である。
その兆候は昨年の世界陸上ブダペストに表れていた。夏場の大会としては気象コンディションに恵まれたこともあるが、3人が1時間17分台、8人が1時間18分30秒以内をマークして日本勢は入賞できなかった。
その背景に厚底シューズが、競歩でも記録アップに関与し始めたことがある。それに加えて以前は20kmと50kmだった競歩種目が、22年以降は20kmと35kmに変更された影響もありそうだ。パリ五輪ではついに、35km競歩が実施されなくなった(代わりに男女混合競歩リレーが実施)。
35kmの人材が20kmに流れてきた、という指摘もされている。世界大会で35kmが実施されない今年については、その通りだろう。その点だけでなく、20kmと35kmと距離差が小さい2種目なら、トレーニング的にも両立できるという見方もできる。オレゴンもブダペストも、両種目を兼ねて出場していたメダリストが多くいた。それぞれの種目に相乗効果が表れるようになったのではないか。
厚底シューズが2種目のトレーニングを両立しやすくしている側面も、もしかするとあるのかもしれない。35kmのトレーニングをしていれば、20km選手としてはスタミナが強化される。国際大会のように前半がスローペースで進めば、スタミナ型の選手が後半まで余力を持つことが可能になり、終盤で強烈なスパートができる。
いずれにしても競歩が、時代の変革期のまっただ中であるのは事実である。
25年世界陸上東京では35km競歩が再実施 金メダリスト・山西の復活も期待
来年9月開催の世界陸上東京大会では、オレゴン、ブダペストと同様に20km競歩と35km競歩の2種目が実施される。今年のように競歩全選手が20kmをターゲットにすることはないが、オレゴン&ブダペストと同様に、2種目に出場してくるトップ選手は多いと思われる。パリ五輪とは異なる状況になるが、両種目を兼ねる選手が強さを見せると予想できる。日本は選手層が厚いため、両種目を兼ねると選考会を勝ち抜くときにリスクが生じる可能性がある。これまでと同様、両種目で代表選手が分かれる可能性が高い。
現時点で厚底シューズへの対応がきる日本選手もいるが、対応に苦労したり薄底に戻した選手が多かった。筋力的な部分で対応しにくいという指摘もあるが、時間が経てば対応策も蓄積されるはずだ。鈴木も池田も薄底で1時間16分台をマークしたように、厚底だけが選択肢とはならない。
外国勢の上位選手層が厚くなっているのは脅威となるが、池田が残り5km、2kmのタイムを、メダルを取った2大会のレベルに戻すことができれば、再びメダルを取ることも可能になる。
そして19年ドーハ、22年オレゴンと世界陸上を2連覇した山西の復活も期待できる。
山西は今年の日本選手権で失格した。厚底シューズへ対応する過程で、悪い動きが身に付いてしまったのだ。薄底に戻したが動きは戻らなかった。
だが5月の世界陸連グランプリ競歩ラコルーニャ大会には1時間17分49秒で優勝した。そのときの2位がA.マルティン(30、スペイン)、3位がC.ボンフィム(33、ブラジル)、B.D.ピンタド(29、エクアドル)。パリ五輪のメダリスト3人に対して勝利を収めた。メダリスト3人に続く5位が池田だった。
山西、池田とも選考会を勝ち抜かなければ世界陸上代表入りはできないが、2人が牽引してきた日本の20km競歩は、来年の世界陸上東京でメダル争いができる。
(TEXT by 寺田辰朗 /フリーライター)