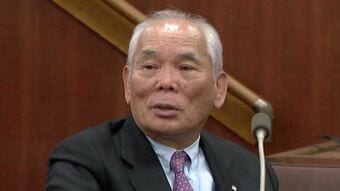去年12月、沖縄本島内で16歳未満の少女を誘拐し性的暴行を加えたとされる米空軍兵の初公判が、7月12日午後、那覇地裁で開かれる。同日朝、RKBラジオ『立川生志 金サイト』に出演した、元サンデー毎日編集長・潟永秀一郎さんが、沖縄で相次ぐ「アメリカ兵による女性暴行事件」と、それを公表しなかった政府の対応について「忘れてはいけない、根深い問題」とコメントした。
「地元は蚊帳の外」日米の通報体制が形骸化
経緯を振り返ります。最初に発覚したのは、去年の12月に沖縄のアメリカ空軍に所属する25歳の兵士が、公園で16歳未満の少女に声をかけ、自宅に連れ込んだうえ、性的暴行をしたとされる事件です。家族から通報を受けた県警は、防犯カメラの映像から容疑者を特定して今年3月11日に書類送検し、那覇地検は3月27日に起訴しました。
ところが、これが明るみに出たのは、それから3か月近くたった6月25日。地元の民放が報じて、県が外務省に確認したところ、外務省は既に米兵が起訴された日、駐日大使に抗議していたことが分かりました。地元は蚊帳の外です。
沖縄では1995年9月、3人の米兵が小学生の女児を拉致して性的暴行をするという痛ましい事件が起きて県民の怒りが爆発し、大規模な抗議集会が開かれました。その後、容疑者の身柄引き渡しなどについて日米地位協定の運用が一部見直されたほか、沖縄で公共の安全に影響を及ぼす可能性のある事件が起きた場合、地元に情報を伝える経路も定められました。
しかし今回、情報は政府レベルでとどめられ、地元には一切伝えられませんでした。沖縄県の玉城デニー知事は「信頼関係において著しく不信を招くものでしかない」と憤りましたが、発覚の翌日に会見した外務省の報道官は「常に関係各所への連絡通報が必要であるという風には考えていない」と述べ、問題はないとの認識を示しました。理由は「被害者のプライバシー保護」です。
事件を明らかにできない「タイミング」があった?
ただ、この説明には各方面から疑義が示されました。「政府には、事件が明るみに出たら困る、別の理由があったのではないか」と。それは時期的な問題でした。
まずは、事件が起きた昨年12月です。米軍普天間飛行場の辺野古移設を巡り、国は月末に知事に代わって工事を承認する「代執行」を行いました。知事は岸田首相との面談を求めましたが実現しないまま、年明け1月に着工し、知事は「民意を軽視している」と強く反発していました。
次に、起訴された3月末です。首相は4月8日から国賓待遇でアメリカを訪問し、首脳会談や議会での演説が予定されていました。まさに外務省マター、しかも最重要案件で、起訴はその直前というタイミングでした。
政府側は隠蔽の意図を否定しましたが、私には「さもありなん」と腑に落ちる話でした。さらに5月には、アメリカのエマニュエル駐日大使が、台湾に近い日本最西端の与那国島を初めて訪れ、「戦争を防ぐいちばんの方法は確かな抑止力だ」と日米同盟の重要性を訴えるセレモニーがありましたが、もし事件が発覚していたら実現しなかったかもしれません。政府、とりわけ外務省にとって、95年の事件を想起させる今回の少女暴行事件が、最悪のタイミングだったのは間違いないからです。