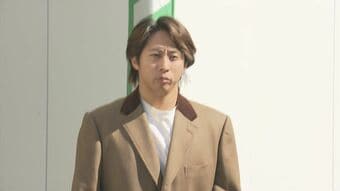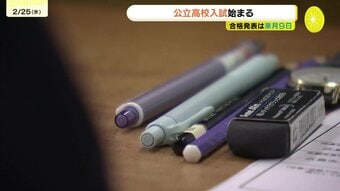緊張や不安など心理的な要因も大きく 家庭の対策 “4つのポイント”
本名アナ
私なんかそうですけど、「あ、トイレ行くの忘れた」などで、例えばバスに乗った時に、そう思うだけで結構ピンチみたいな心理的な部分がすごくあるような気がするんですけど、これはあり得るんでしょうか?
はしもとクリニック 橋本成史 院長
「今トイレに行っちゃいけない」という状況がありますよね。それが心理的な要因として影響を与えることは十分に考えられます。要するに心理的な緊張など不安がストレスになって尿意を強く感じさせることがあるんですね。こういう心理的な要因というのは非常に膀胱の機能に及ぼす影響が知られてます。
例えば200人の前で普通に喋らなきゃいけないというようなときに、壇上に上がる前に突如として、オシッコが近くなったりドキドキしたりすることがありますよね。そういうような状況のときに起こる場合があります。
本名アナ
治療方法は、ひどい場合は薬であったり手術だったりすることもあるんでしょうか?
橋本院長
手術は病気によってはですけど、まず背後にどういうものがあるかいうのを調べてから、何か病気を見つけたら、それに対してまた検討していくということになります。
本名アナ
通常の場合どうなんでしょうか。投薬などである程度改善されるんでしょうか?
橋本院長
投薬と、色々な行動療法とか、生活習慣を改善することで、症状が改善する可能性はあります
家庭でも簡単にできる 普段から心がけたい4つのポイント

本名アナ
少なくともほっとくのはよろしくないということなんですけども普段から何かできる対策を心がけておくと良いことってありますでしょうか?
橋本院長
症状を緩和するための普段からの対策としてはですね、生活習慣の改善とか行動の療法を中心に行われるといいと思います。要するに自分で家でやるということなんですけども、
1番目はカフェインとかアルコールは膀胱を刺激する可能性がありますので摂取を控えましょう。
2番目ですけど、適切な体重を維持することで膀胱への負担を軽減できます。
本名アナ
体重関係あるんですか?
橋本院長
関係あります。非常に肥満がある人は、他の内臓が膀胱を抑えてしまう。それで膀胱へ負担をかけてそれでできやすくなる。
3番目ですけど、膀胱のコントロール改善するために筋肉を強化する方法ですね。骨盤底筋トレーニングとかヘーゲル体操というのがあるんですけど、これはネットで図解で紹介されてるので調べてみてもらって、簡単にですので家庭でできます。
4番目はトイレの時間を決めて定期的に排尿する癖をつけて、膀胱の過活動を抑えることが可能と言われています。
本名アナ
我々が普段から心がけられるのはこの4つということになりますね。こうしたことを皆さんぜひ参考にしていただきたいと思います。

( RCCラジオ「本名正憲のおはようラジオ」 6月21日放送 )