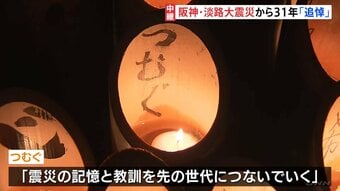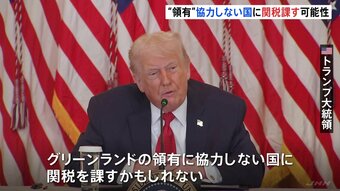日常的に「やさしい日本語」を使う人が増えてほしい
主催した「こまえにほんごしえん・日本語スクール」は2021年に市民団体として設立、24年にNPO法人になり、外国人児童への日本語指導、生活適応サポートなどさまざまな取組みをしてきました。
現在30人ほどの登録メンバーがいて、児童が学校で受けとるプリントを「やさしい日本語」に翻訳する支援なども行っているそうです。今回の講座に参加したトークパートナーは同NPOが開催している日本語スクールや文化交流イベントに参加している人たちです。代表の檜垣寿子(すみこ)さんに、イベント開催の理由を聞きました。

NPO法人こまえにほんごしえん・日本語スクール 代表の檜垣寿子さん
「狛江市は近隣の市町村に比べて外国人サポートが少し遅れていまして、その中で私たちはもともと児童を対象にサポートしていたんですけど、学校や行政の現場で、難しい日本語が使われてしまうんですね。たとえば外国人の児童が転入してきて、転校手続きがありますね。そこで分からない日本語の書類を大量に渡されるというのがありまして、私たちがそこにいて教えられればいいんですけど、毎回私たちが出向いていってサポートするというのはとても難しくて、だったら直接外国人の方と接する人たちがやさしい日本語を使えれば自然なサポートの輪が広がるんではないかと思いまして、今回、やさしい日本語をテーマにいたしました」
東京都でも在留外国人の多い地域では行政、教育、医療などの場で「やさしい日本語」を使って対応しているところもあります。しかし狛江市など東京西部地域は比較的外国人の人口が少なく、行政のサポートが追いついてない場合もあります。そうした地域でも、日常的に「やさしい日本語」を使う人が増えてほしいと 「こまえにほんごしえん」は今回、初めてこの「実践講座」を開催したそうです。
講座の感想を、日本人の参加者と、トークパートナーとして参加していたフィリピン出身の女性に聞きました。
日本人の女性
「私はNPOの日本語支援の団体に入っていまして、勉強会ということでこの講座を知りました。熟語などをわかりやすく外国人の方に伝えるのはとても難しくて、気をつけて使いたいと思いました」
日本人の男性
「僕も日本語支援に入っていて、そのPRで知りました。日常使っている日本語がいかに難しくなっているか、というのをまざまざと知らされたという感じです。何回か受講して、身についていくのかなと思いました」
日本人の女性
「私は日本語教師をしていたので、市役所の書類とかが、もっとわかりやすい日本語になればいいなと思っていたんです。単なる方法として勉強したのではなくて、各テーブルに外国人の方が入って、わかるかどうか伝えてみましょうという機会はなかなかないので、本当にいいプログラムだなと思いました」
フィリピン出身の女性
「難しい言葉はほんとにわかりませんでした。だからもう一度お願いしますと、お願いしたことが多いです。やさしい日本語は楽しかったです。やさしく、短くなって、だから、すごいありがたいですよ」
今回の講座の日本人参加者は、外国人の日本語支援に関わる方が多かったのですが「こまえにほんごしえん・日本語スクール」代表の檜垣さんは「やさしい日本語」を使える人材をもっと増やして教育の現場だけでなく、多くの場面で外国人の支援体制を広げていきたいと話していました。
同NPOは毎月3回程度、文化交流イベント「にほんごサロン」を開催しているほか、今後、冬に向けて「やさしい日本語」を使って防災ポイントや防災用語を学ぶ外国人向けの防災訓練などを企画しているそうです。
また講師を担当した「kokohana やさしい日本語でつながる八王子の会」は8月、9月に「やさしい日本語」のイベント開催が決まっています。基本的に誰でも参加できるイベントですし、外国人との接し方を考える場として多くの人に興味を持って欲しいと思いました。

(TBSラジオ「人権TODAY」担当:藤木TDC)