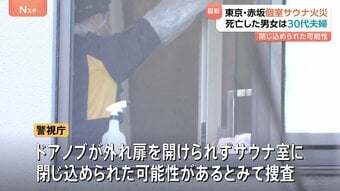焦点は新たな財政健全化計画に
しかし、PB25年黒字化目標が復活した最大の理由は、何と言っても、25年度がもう来年度だからです。
目標に明記しようが、曖昧にしようが、その答えは1年後には出ているわけで、論争としてはあまり意味がありません。
それよりも、2026年度以降の新たな財政健全化目標をどう設定するかに関心が集まります。
今後、中長期的な目標を、引き続きPB黒字化に置くのか、債務残高そのものの削減にまで踏み込むのか、今後の議論の大きな焦点になります。
PB黒字化は最初の第一歩に過ぎない
そもそもPB=プライマリーバランスとは、借金以外の収入で、借金の返済や利払い以外の支出を賄えるかどうかという指標です。
例えば、政府の今年度予算で言えば、予算規模113兆円のうち、国債発行による歳入が35兆円あり、その一方で国債の元利払いの歳出が27兆円あるので、政府予算のPBは8兆円もの赤字と言うことになります。
これがゼロになって、初めて国債の発行残高が横ばい、つまり増えない状況になるわけです。
骨太の目標は、国と地方を合わせたPBの黒字化ですから、先に述べたように、国単独の収支より黒字化が近い状態になっていますが、いずれにせよ、PB黒字化は、これ以上借金が増えない状態を作り出すだけで、借金の残高が減るわけではありません
財政健全化には息の長い取り組みが必要
重要なことは、長期的に財政健全化への取り組みを継続し、それが金融市場にも理解されることです。
異次元緩和の終結で金利ある世界に入った以上、長期金利や為替の動向には、「国への信認」がダイレクトに反映されと、考えるべきでしょう。
すでに円安に歯止めがかけられないという「危険な兆候」さえ、現に表れ始めています。
先進国で突出した財政赤字を持つ日本が、ひとたび市場の信を失えば、国民生活に深刻な影響が出かねません。
その一方で、無理な増税や急激な歳出カットで。辻褄合わせのように単年度で健全化を演出したところで、何の意味もありません。
財政収支が改善しても、成長しない経済になってしまえば、それこそ本末転倒です。
財政健全化への息の長い意志を持ちつつ、現実の経済状況を見ながら、成長を促す政策運営を行うという、当たり前の取り組みを、忍耐強く続ける以外、方法はありません。
「いくら国債発行しても問題なし」とか、「何が何でも財政再建」といった極論に流されない議論が必要に思えます。
播摩 卓士(BS-TBS「Bizスクエア」メインキャスター)