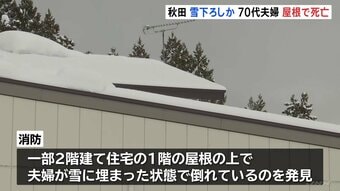専門家「干拓事業は致命的な影響与えた」奪われる海の栄養分
佐賀県で最も諫早湾に近い、太良町の漁場。大鋸武浩さんは、太良町のノリ漁師。
ノリ漁師 大鋸武浩さん
「私は諫早湾干拓の影響が大きいということを確信しています。あれが出来上がってから冬の赤潮が大発生するように、拡大がひどくなっているのは肌身に感じております」
これまで30年間、ノリの養殖を続けていたが、ついにこの冬、ノリを諦め、廃業した。

ノリ漁師 大鋸武浩さん
「さすがにもうダメだろうと、去年、ノリ漁が終わった段階で思いました。佐賀県西部地区、10年後15年後になるともういなくなるんじゃないかと、ノリ業者が。それくらい海の状況は悪化しています」
有明海に起きた異変。諫早湾の閉め切りから四半世紀が過ぎ、海の研究者たちによってその理由が明らかにされてきた。
海の栄養分となる窒素やリンは、川からもたらされる。有明海では、九州一の大河、筑後川がその主な供給源となる。
有明海の奥には、かつて反時計回りの強い潮の流れがあり、筑後川からの栄養分を程よくかきまぜ、分散させていた。

有明海の潮流を調査してきた 堤裕昭 熊本県立大学学長
「反時計周りがなぜ起きるのかというと、上げ潮の時に、西側は諫早湾に入る水と佐賀県の奥に入って、2つに分かれるから水が単純に半分になるわけですよね。東側にはそういうのはないから、まっすぐ上がる。それによって反時計回りの潮流が起きる。諫早湾の干拓事業は致命的な影響を与えた。あそこを閉めきった分、中に水が入らなくなった。そうすると、東側とあまり変わらなくなっちゃうんです。そうすると、ただの往復流になってしまうから、筑後川から入ってきた窒素とリンはそのまま行ったり来たりして、ずっと留まる分が増えるわけです」

諫早湾を閉めたことによる潮流の変化が、筑後川の栄養分を停滞させ、プランクトンの異常増殖「赤潮」を引き起こし、海の栄養分を奪う。
大量のプランクトンはやがて海底に沈むが、特に水温の高い夏は、その死骸が分解される際、大量の酸素を消費し、海底は酸素不足になる。
酸素不足の海底では、生物は生きられない。貝など、海底にすむ生き物は魚介類のエサとなるため、さらに多くの海の生き物が影響を受ける。