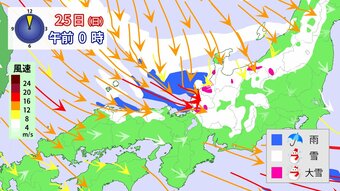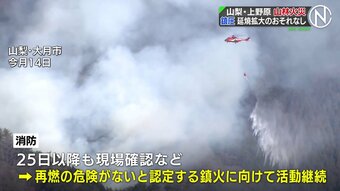「琉球の声」誕生
川平
全く空白ですね。しかし、私の兄の朝申※(1908~1998)というのがですね、沖縄人側の政府、あのころは沖縄人側の政府を沖縄民政府と言ってたわけですね。
※川平朝申 (かびら ちょうしん) 当時沖縄民政府勤務 のち「琉球の声」放送局長
そこに文化部というのがありまして、ラジオをやろうという提案をするわけですよ。で、提案をしますとですね、電気もない、ラジオを持ってる沖縄人がいない。まずは住宅だということで、荒唐無稽扱いされるんですね。
私の兄は臆することなく、実際にアメリカ軍政当局に持ってったら「お、これはグッドアイデア」と。むしろ軍政当局のほうがこれを取り上げるということになるんですよ。だから、その意味では、私の兄の朝申、私事ではありますけれども、「ラジオというものはまず電波を出さなければ、誰も聞かない」と。「みんなラジオ受信機を用意してラジオが始まるのを待つというものではない」と。「しかもラジオを始めれば、これを聞きたいということになって…」、今で言えば電化ですよね。
※(1950年)当時の沖縄本島の電力事情は、1953年に牧港火力発電所が石炭火力による電力供給を行うまでほぼ自家発電に頼っていた。1954年、琉球電力公社発足、復帰後沖縄電力となる。
各務
そうして「琉球の声」、通称ラジオ沖縄っていうのができた。川平さんのお兄様の朝申さんが発議されて、そして軍政府が認めてですね、その局長に任命されたのも、軍政府から任命されたわけですか。
川平
そうです。
※「琉球の声」放送(通称ラジオ沖縄)は1949年米軍により始まった日本語試験放送を引き継ぐかたちで1950年1月21日開設。現在のラジオ沖縄(ROK)とは別の会社。その後、地元紙沖縄タイムスが中心になって設立した琉球放送(RBC)が引き継いだ。
「琉球の声」が放送を開始した時には、ほとんどの番組はNHKの番組を中継したんですよ。で、NHKはですね、あの当時短波で番組を送ってたことがありますから、その短波を受けて再放送したと。
それについては、当時、日本の方も占領下ですから、これはもうアメリカの、沖縄の軍政府と、本土のCIE※との間で連絡がついていて、それでNHKの番組というのは安全であるというような気持ちもあったと思うんですね。ですからNHKの番組をほとんど放送してました。
※CIE(Civil Information and Education Section) 民間情報教育局 放送などを管轄する部局。
各務
当時の番組は沖縄県人にはどういう受け取られ方でしたか?
川平
喜ばれてた面はありますね。やはり本土から引き揚げてきた人たちがいますから、本土で聞いたものを沖縄でも聞けるということで、非常に喜ばれました。
さらに言えば、私は1952年NHKのアナウンサー養成所に参加して研修を受けるということも出来ましたから、そういう意味ではNHKは非常に好意的だったと思います。
各務
ただ、この放送史によりますと、1951年から53年の間は、大体NHKからの番組が50%あったのが、55年から米軍の意向があって、NHKの番組は1日2時間に減らされたとあります。これはやっぱり朝鮮戦争とか何かと関連があるでしょうか。
川平
ええ。これは明らかに日本が1952年に独立を回復しますよね。そうなるとNHKの放送は危険であると、何でも報道をしたわけですからね。もう検閲がなくなってますし。もうそれは当然のことなんで。それで沖縄で面白いことが起きたんですよ。
各務
NHKからの番組が減るということは、自主制作のものを増やさなくちゃならないということですね。
川平
そうです。で、その頃から、沖縄の制作能力というのはかなり高まってきたと思います。それで一番問題になったのはニュースなんですよね。で、ニュースは自己取材をやってたわけですね。
いっぽうで検閲は続いてました。