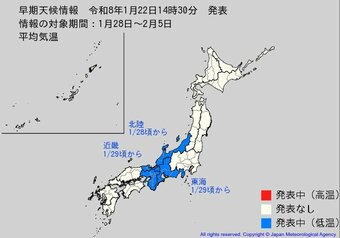「千代田証券事件」がヒント
さっそく粂原らは野村証券だけでなく日興証券、大和証券、山一証券にも「小甚ビルディング」や小池隆一関係の取引口座がないかどうかを照会、さらに銀行口座を確認するなど、ねばり強く資金の流れを追った。
その結果、総会屋「小池隆一」が、野村証券など4大証券だけでなく多数の上場企業の株式を大量に保有し、その資金は、トップバンクの「第一勧銀」からの「融資」の形で調達していたことが判明した。そうした大株主の立場で金融機関に圧力をかけていた。「小甚ビルディング」は、その小池隆一に利益を流し込むための「ダミー会社」だったのだ。
野村証券は自己売買によって得た利益を、あたかも小池側から委託注文(直接注文)を受けた取引であるかのように装い、「小甚ビルディング」に利益を付け替えて提供していた。もちろん、こうした「利益の付け替え」は証券取引法で禁止され、「総会屋への利益供与」は商法違反にあたる。
粂原ら「SEC」がこの「付け替え」の手口を解明できたのは、実は過去のある事件がヒントになっていた。その事件とは、これより前に告発した中堅証券会社の「千代田証券事件」だった。この事件は顧客からの要求を受けて、千代田証券の幹部らが「損失補てん」を行っていたもので、その際に同じ手法が使われていたのである。手口としては、千代田証券が購入した「値上がり株」を、最初から顧客が購入したように装う「付け替え」が行われており、操作にはコンピューターが使用されていた。
「取引の市場となる東京証券取引所との交渉に、現場が苦労しながら『自己売買を委託取引に付け替える不正』を解析するノウハウを得た」(粂原)

それはどんなノウハウだったのか、捜査の裏側を聞いた。
「証券会社内のルールで、『自己売買』の注文を出すときには、たとえば「1」と入力し、『委託取引』注文を出すときには、「2」と入力するように定められていたとする。
『東京証券取引所』のホストコンピュータ上の当該取引の記録が「1」であるのに、『証券会社』の記録だけが、『委託取引』を示す「2」に変わっているのはおかしい。同一の取引にもかかわらず2通りに注文がだされているのは「付け替え」の痕跡であろうと。つまり、東証の記録は事実であって、変えられないため、やはり『証券会社』側の記録が改ざんされた疑いが強いということになる」(粂原)
当時、東証のホストコンピュータ上には、一つの取引注文につき何十桁もの数字が並んで表示されており、その数字の配置によって銘柄、数量、「売り」か「買い」かの区別、「委託取引」なのか「自己取引」なのかの区別、金額などが分かるようになっていた。
そうした数字をひとつひとつ分析することによって、不正な「利益提供」の仕組みを解き明かしたのだ。「SEC」が独自に手掛けた「千代田証券事件」の経験があったからこそ、実を結んだ調査と言える。
しかし、「SEC」のチームはこうして野村証券による利益提供の突破口を次々に切り開いていく中で、組織としてクリアしなければならない、大きな課題にも直面していた。
(つづく)
TBSテレビ情報制作局兼報道局
「THE TIME,」プロデューサー
岩花 光