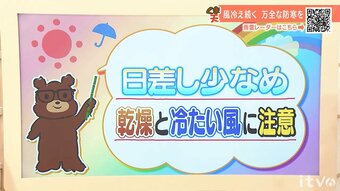減る手取り額、止まらない物価上昇に値上げの波 都道府県別で200万円の年収差も…
厚生労働省が3月に発表した「令和5年賃金構造基本統計調査」によると、一般労働者の月額賃金は、前年比2.1%増の31万8300円になったとのことだ。
しかし、これはあくまで平均。この平均値を超えている都道府県は、わずか5県で、栃木県、東京都、神奈川県、愛知県、大阪府しかない。残り全ての都道府県は平均以下だ。
また、もっとも年収が多い東京都の年収は581万円、最も少ない青森県は384万円となり、約200万円もの差となった(厚生労働省「令和5年賃金構造基本統計調査」をもとに独自に計算した都道府県別の年収ランキングは画像でご覧いただけます)。
もともと給与が少ない都道府県で、手取り額が減るとますます生活は苦しくなる。
岸田政権肝いりの「物価高騰対策」による電気・ガス料金の負担軽減措置は、今年6月から半分に縮小することに加え、再生可能エネルギー発電促進賦課金単価、いわゆる再エネ賦課金は1.40円/kwhから3.49円/kwhに引き上げられる。
止まらない物価上昇に値上げの波…。高齢者の健康寿命が延びているのであれば、働く世代の生活に直結する「手取り額」を減らさないよう、少なくとも天引きされる社会保険料を増やさないため、「医療費」についても「年金」についても、抜本的な議論が必要なときではないだろうか。
政府が推進する定額減税で「所得の下支えを実感」できるは、2025年5月までのあと1年だ。