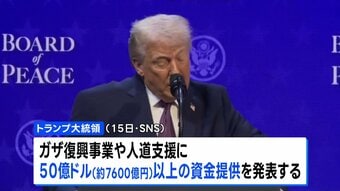「この国には“安全保障基本法”っていうのはない」
もしも国会で原潜保有が議論されたとしても、その是非、その運用…すべて閣議決定で事が進むのだろうか…。イギリス、イタリアと共同開発する次期戦闘機の輸出をめぐっていわゆる武器輸出三原則が閣議決定で改定された。この重要な案件を法律化することなくその都度閣議決定、つまりその時の政権の方針で決まっていくのは今や日本の“慣習”になっている。
実は武器輸出三原則を法制化しようという案はあった。1970年公明党の正木良明議員が「日本は平和国家として武器は輸出しないのだと言うために『武器輸出禁止法』を作ろうというお考えはないかどうかお聞かせいただきたい」と時の佐藤栄作総理に問うた。だが、佐藤総理はこう答えている。
「武器輸出についての三原則、これで私は事足りておるように思います。もう一つ申し上げますが、何を武器というかこういう問題も一つあると思います…」
こうして法制化は見送られ、その後、その時々の閣議決定によって三原則は徐々に緩和されてきた。憲法学が専門の青井教授は言う…。

学習院大学 青井未帆 教授
「私は多分にこれ(法制化せず柔軟に対応してきたこと)は政治の胆力の問題なんじゃないかと思うのですけれども…(中略)(規則に)正当性を与える機関(=国会)をこのような形でショートカットするというのはどう考えてもよろしくありませんので、何らかの形で議論を立てていく必要がある…」
因みに武器輸出に関わるの法律としてアメリカには『武器輸出管理法』、イギリスには『2002年輸出管理法』、ドイツには『戦争兵器管理法』などがある。
『戦争物資法』を有するスイスのバーゼル大学、ゴッチェル教授は「閣議決定による安全保障政策の転換はスイスではありえない」と断言した。
そして、石破氏もまた法制化を提案する一人だ。

自民党元幹事長 石破茂 衆議院議員
「臨機応変といえば聞こえはいいが、どういう考えで(武器を)輸出するのかしないのかというような問題を、その場その場で決めていくというのは国家の在り方として決していいことだと私は思っていない。この国には50くらい“なんだかかんだか基本法”っていうのがあるんですよ。でも“安全保障基本法”っていうのはないんです、この国には…。非核三原則であるとか、専守防衛であるとか、武器輸出三原則であるとか…、法律でもないけど閣議決定でもない、でも国是ですよね。まぁ閣議決定したものもあるけど…。これは、我々がいつも政権を持っているとは限らない。ぜんぜん違う考えを持った政権ができることだって否定はしない。やっぱり法律っていうものを作って、そこへの過程でいろんな議論が行われた方が国家の在り方として正しいと私は思っています」
さらに石破氏は、佐藤総理の時代は東西冷戦期でバランスオブパワーが利いていて均衡が保たれていた時代だった。だが今は事情が違うという…。
自民党元幹事長 石破茂 衆議院議員
「アメリカの力が落ちてきた。ウクライナだって、ガザだって、底流にあるのはアメリカの力が落ちてきたことだからね。だからこれから先、世の中がややこしくなる。その中にあって…(中略)(高額な武器は)共同研究、共同開発、共同生産、共同使用していかないといけない。その時に“日本はこういう方針ですよ”ってきちんと法律で決まっていることは国際社会において大切なこと…」
小泉准教授も法制化には賛成だが、問題はその内容の難しさだという。
東京大学先端科学技術センター 小泉悠 准教授
「“一切武器を輸出してはいけない”って書けるんなら話は簡単だが、現実にはそうはならない。さっき佐藤総理が“何が武器なのか分からない”という(定義の問題を)60年前でさえ言っていたが、今もっとわからない。ソフトウエアであるとは、半導体がロシアにわたるとか…、色んなものがデュアルユース化していて軍事物質かどうか…(中略)考え抜いて法律を作る過程が日本としていい勉強になると思います」