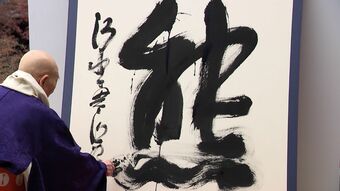5月も半ばです。この時期に心配されるのが、いわゆる「五月病」です。進学や就職など生活環境が変わることでストレスを抱えやすくなり、心や体に不調を抱える人も現れやすいといいます。精神科医の岡山大学学術研究院社会科学学域(文学部)の 耕野敏樹准教授に「五月病」への対応方法などを聞きました。
耕野准教授は、「昨年の今頃はコロナ明けのタイミングでもあり、五月病の症状を感じる人が多かったが、今年もまだコロナ禍の影響を引きずっている印象がある。症状が出る前に楽しんでできていたこと、人と交流していたことを思い出すことが大切」といいます。
(2023年5月の記事再掲です)
「五月病」今の時期、不調を訴える相談が増える
(街の人)
「起きるのとかしんどかったり、めんどくさいなとか」
「GW明け、最初はだるいかなと思ったことは結構ありましたけど。朝と夜で気温が違うので大変ですね」
「眠れなくなっています。梅雨の前後は、そういう感じがありますよね」

いまの時期に心配されるのが、いわゆる「五月病」です。岡山市北区の岡山県精神科医療センター・医師の耕野さんは「日常生活における環境の変化により、特にこの時期不調を訴える相談が増えている」と言います。

(岡山県精神科医療センター 耕野敏樹 医師・当時)
「日本の場合は、4月に色々な社会環境が変わる出来事が多いものですから、どうしても『1カ月くらい自分なりに工夫をしてきたけど、やっぱり上手くいかない』と相談に来る人が多くいる」