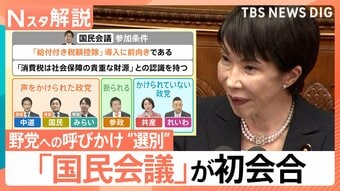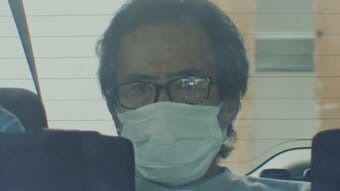夜型の子どもにしてあげられること 大切なのは光
──子どもが選んで夜型なわけではないとすると、その子の不調はその子の責任とも言えないように感じます。なにか夜型の子どものためにできることはあるのでしょうか。
「体内時計への影響が一番大きいのは、目に入る光です。ですので、光の取り方には気をつけてください。
まずは、起きる時の光です。朝の時間帯に強い光が目に入ると、体内時計への『もう朝ですよ』というシグナルになり、時計が進む方向にリセットされます。
夜型になりがちな子どもは、朝は無理してでも起きて、明るい光を目に入れましょう。窓の外を見る、ないしは外に出る。空の光は、屋内の光よりもはるかに明るいので大事です。
次に、夜の光です。逆に夜は、明るいところに行っては駄目です。明るすぎるところに夜いると、体内時計への『まだ昼だよ』というシグナルになります。時計が遅れる方向にリセットされてしまいます。そうすると、ただでさえ夜型なのが余計夜型になり、結果としていつまでも夜眠くならなくなります」

──夜の明るいところというと、例えば繁華街などですか?
「日本は家の中も明る過ぎると思っています。ですので、リビングやダイニングといった家全体を少し暗めの環境にする、というのを私は薦めています。
人間は昼行性で、昼間に行動する動物なので、強い明るさは脳を活性化させます。逆に、暗くなると脳がリラックスするようにできているのです」
──夜型の子どもがもっと生活しやすくなるような、根本的な解決方法はないのでしょうか。
「これは難しい問題です。残念ながら、世の中は朝型に有利なようにできています。
朝型と夜型の分布を見ると、朝型と夜型の中間の型が一番多いカーブとなり、きれいな『つりがね型』を描いています。実は、半分までとはいかなくても、3分の1くらいの人は『筋金入りの夜型』で、多かれ少なかれ苦労しています。
理想は朝型や夜型といった個性に合わせた社会にすることです。だけれど、学校が個々人に合わせるのはなかなか難しいと思います。
だから、せめて大人になったらフレックスタイムにしてほしいです。夜型の人は遅く来て、遅くまで仕事して、朝型の人は早く来て、早く帰ってというような社会です」
◇
聞き手:TBSテレビ デジタル編集部・久保田智子 構成:影山遼
(TBS NEWS DIGオリジナルコンテンツ「SHARE」より)