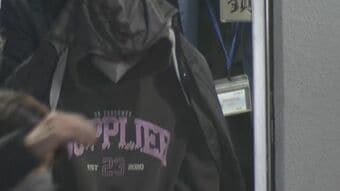いじめをなくす 今こそ“予防を”
山本恵里伽キャスター:
「いじめ」は昔からずっと言われ続けていますが、どうしてなくならないのでしょうか?
「news23」編集長 川上敬二郎 記者:
1個言えるとしたら、今まであまりに事後的な対応に偏りすぎてたんじゃないかなと思っていて、もうちょっと予防的な発想でいろいろと取り組みが必要だというふうに思うんです。
どこから手をつけたらいいのかというと、問題が本当に複雑で重層的ですから、子どもを中心に考えていこうと思います。

例えば、子ども・家庭の問題でいえば、「スマホ依存」があって、スマホ依存の子どもたちは、実はイライラするとネットいじめしちゃうとか、そういうのもあるんです。
先生の問題でいえば、「ブラック勤務」というような話もあります。先生たちは、忙しすぎるといじめ対応なんてできません。
山本キャスター:
特に今、教員不足が叫ばれていて、「もう先生になりたくない」という人たちも多いじゃないですか。そうすると、先生たちの負担がどんどん増えて、逆にいじめ予防から遠ざかってしまっていますよね。
川上記者:
質の問題というのはありますね。だから、先生によっては気づかないふりをするというようなケースだってあるんです。
山本キャスター:
それは現実としてあって欲しくはないですけどね。
川上記者:
学校に広く視点を持てば、「予防授業」や「ブラック部活」など、どのようにしていけばいいか。
「ブラック部活」なんかは、「いらない子」というふうな意味で、それがいじめに繋がってしまうのもありますし、「予防授業」もどういうふうにすればいいのか。純潔主義みたいなのに訴えるだけの授業もあるんですよ。
山本キャスター:
でも今回取材された授業だと、生徒たちが本当に議論をしてましたよね。
川上記者:
こうやって早めに議論をすれば、いじめといじりの分かれ目を考えられるので、議論するような対話の授業、これも必要だと思いますね。
山本キャスター:
人によっては「これが嫌だって思うんだ」というようなことに気づくことが大切ですよね。
川上記者:
対話を通して、「人によって感触が違う」、それをわかって欲しいということです。
山本キャスター:
そして私達含め、社会全体がしっかりと関わって問題意識を持っていく必要がありますね。