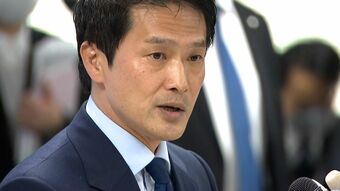「大人の経験値だけでは守れないものがある」
この日、訪れたのは兵庫県立舞子高校の環境防災科。阪神・淡路大震災を契機につくられた全国初の防災に特化した学科で、齋藤さんも講師として何度も訪れている。だが、生徒たちは阪神・淡路大震災の経験はなく、東日本大震災もほぼ記憶にない世代だ。

「東日本大震災では、大人の経験値で『ここは大丈夫だ』と思った避難場所が津波に飲まれた。どこかでスイッチを入れて逃げなきゃいけない」
大人の経験値だけでは守れないものがあること。想定外を想定しないと救えないものがあること。将来の地域の防災リーダーに語りかける。
“テーマのない対話”が防災の力に
齋藤さんの授業で特徴的なのが、“テーマのない対話の時間”だ。コミュニティボールと呼ばれるものをグループ内で回しながら手にした人が思いや考えを自由に吐露し、周りはしっかり話を聞く。

「学校の大切さってどう?」
「当たり前の場所。安心感」
「災害時はいつもと違うからこそ、いつもの学校に行きたくなると思う」
授業後、生徒に話を聞くと、「災害は何の準備もない状態から始まるから臨機応変に自分たちが対応するのが大切」と思いながら“テーマのない対話の時間”にも臨んでいるとのこと。日常の中で判断力や柔軟性といった、防災で必要な力を高めていた。

生徒たちは能登半島地震の被災地にもボランティアに行く予定だ。齋藤さんは何よりも、相手のつらさや悲しみに共感する気持ちを強調した。

「『そうだったんですか、たいへんでしたね』とうなずいて話を聞くこと。答えの出ないものが災害の時とても大事なんだよ」