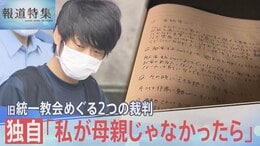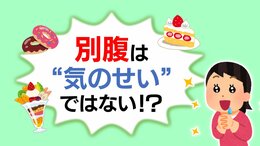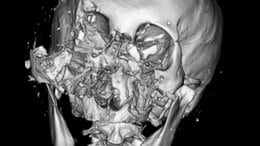日産はコメントを発表したのみ
日産は1月に36社に減額分の全額を支払ったことを明らかにした上で、「大変重く受け止めています。再発防止策の徹底に取り組み、取引適正化を図ってまいります」とのコメント発表をしました。
しかし、記者会見などを行わず、経緯などについての説明を避けています。日本商工会議所の小林健会頭は「社会的な影響が大きい。トップが出てきて説明する責任がある」と、厳しく指摘しています。
「公正な取引」なしに「経済の成長」は実現しない
中小企業庁による価格転嫁に関するアンケート調査があります。
23年9月時点で、労務費を含めたコスト上昇分をどの程度価格転嫁できているかを聞いたところ、全体の平均は45.7%でした。業種別では、「自動車・自動車部品」は、44.6%と平均よりやや低く27業種中17位でした。
最下位は「トラック運送」の24.2%。ちなみに、下から2番目が「放送コンテンツ」の26.9%であったことも、明記しなければなりません。
全体平均でコスト上昇を半分も転嫁できていない現状は、中小企業による賃上げのハードルの高さをうかがわせる数字です。
価格転嫁を進めるためには、政府による「呼びかけ」だけなく、息の長い取り組みが必要です。何重にもわたる下請けが存在し、しかも系列化によって垂直統合されているという、日本的な産業構造も大きな要因だからです。下請法違反も、罰金は最大50万円です。「公正な取引」が当たり前の社会にするためには罰則強化などの態勢整備も必要でしょう。
日本経済の新たな成長ステージは、1度や2度の大企業の賃上げだけで実現するわけではありません。今回の日産による下請法違反は、その道のりの長さを改めて感じさせるものでした。
播摩 卓士(BS-TBS「Bizスクエア」メインキャスター)