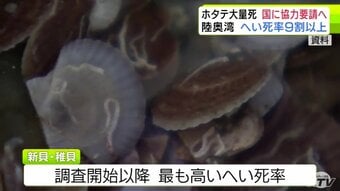災害時、障害のある人にとって避難するための体への負担や時間がかかることなど細やかな対応が求められます。
能登半島地震から約1か月半経ったこの日、青森市の県防災教育センターで障害や難病がある人が就職を目指して通う事業所「A―Run(アラン)」の利用者と職員が防災について学んでいました。
※青森県消防学校 工藤弘樹副校長
「我々は事前にある程度予防できるものは予防しておけば命を守ることができる」
過去の災害などを学んだ後には、よりリアルな訓練に移ります。
※大きな揺れが来ます揺れに備えてください…
※利用者「震度7まで行くと今まで体験したことのないジェットコースターに乗っているような感覚でぜんぜん抗えない感じで自然が怖いなと思いました」
地震体験装置で最大震度7の揺れを体験。東日本大震災や今後想定される南海トラフ地震などの揺れが再現されています。このほかにも消火訓練や煙が充満する部屋から抜け出す体験も行われ、参加者たちは防災への理解を深めました。
※利用者「災害にあったらどういうふうな動きが実際できるんだろうと備えについての学びを感じてきょうの避難訓練も出てみました」
こうした学びを定着化するため「A―Run(アラン)」では、利用者と職員が月に1回のペースで開かれる「リスクマネジメント会議」で課題と対応策を共有しています。
※利用者「本当に火事になった時にできるのかなと思った」
事務所の代表「腕がこうなっているとしゃがめない。低い姿勢になれない」
事業所の職員「はぐれないようにと考えたらどうやってひなんすればいいのかな」
自身も視覚障害があり腰椎疾患の後遺症のため日常生活では杖が必要な齋藤康生代表は利用者と職員、双方向の対話を重視しています。
利用者の声が反映された事例が1階にある出入口の構造に潜む危険性でした。
※A―Run 齋藤康生代表
「鉄板のドアがあり指はさみ事故、ヒヤリハットがあった。『そもそもこのドアを使わなければいいんじゃない』というのが出されたので、その日からそのドアは使っていません」
事業所は障害者が働き始め、職場に定着することを目指しているため「自立」を重要視しています。誰もが困難な環境に置かれる災害時に少しでも「冷静さ」を保つために必要なのは事前の準備です。
※A―Run 齋藤康生代表
「避難することで障害持っていない方に迷惑をかけることもあると考える人もいると思う。ハンディキャップを持っているからこそ一般の人よりは早く逃げてほしいと思います」
命を守るために必要な行動ー 起こりうる災害に備えて利用者と職員が一体となった取り組みが求められています。