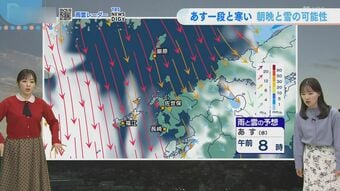■ 避難が 特別警報待ちになっていませんか?
松尾:今回、40年前の気象状況から、防災情報が発表されるタイミングをシュミレートしてますけど、『警報発表』から『土砂災害警戒情報』が発表される段階で、すでに土砂災害が発生してるんですよ。
久富:
長崎大水害の際には、県内の広い範囲で同時多発的に災害が起こりました。土砂災害が、いつどのくらい起きていたのか、時系列で並べてみます。

松尾さん:
実は『特別警報』は2018年から毎年、発表されているんです。毎年です。
(40年前の状況と重ねてみると)特別警報が発表される前段階で、災害が起きてますから、もう『特別警報は、どこかで何かが起きている』と考えなきゃいけないんですよ。
久富:
すでに起きてしまっていると?
松尾さん:
そうです。ですから、この(特別警報が発表された)段階で避難できていないとすれば、なんとか命を守る、動き方を考えていく必要がある。
ところが、その時、どうするか考えるって無理なんですよ。事前に考えておくしかない。
《そういう状況になったら、どういう行動をするか》っていうことを──「よーいどん」をですね、予め考えておいてほしいということです。
久富:
特別警報を待って避難していたら手遅れになることがあるということがよくわかります。
■ 避難スイッチの確認を
松尾さん:久富さんの「よーいどん」はどこですか?
久富:
自治体から『避難に関する情報』がでると、被害に巻き込まれてしまうような大雨の恐れがあると構えます。離れた所に住む家族にも連絡をとりますね。
松尾:
気象庁からの情報だけではなく、自治体が発表する「高齢者等避難」あるいは「避難指示」「緊急安全確保」という防災情報が届きますから、その『前段階で動く』ということが重要です。