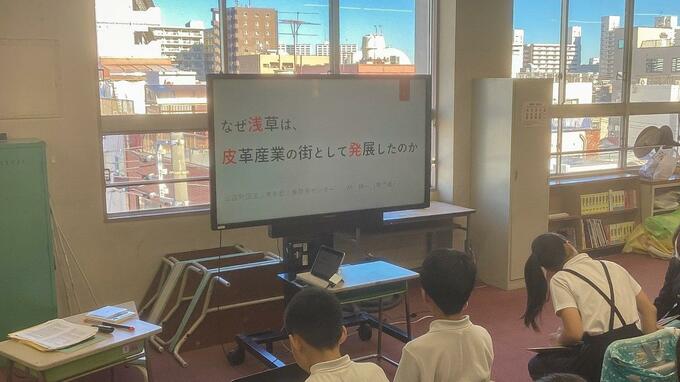台東区立石浜小学校の6年生、2クラス54人が、総合的な学習の時間でこの1年間、台東区の魅力を探ろうと、街を探検しながら皮革産業について学びました。
天然の革材料を扱う地元企業を見学

まずは、インターネットで調べるところから。調べてみると石浜小の校区内にはたくさんの革に関わる店があることを発見しました。財布、ベルト、ハンドバッグにカバン、そして革靴などの履物。昔よりは減りましたが、台東区は革製品製造業や革材料、革靴などの卸問屋が集中している地域です。

6年生たちは革靴の工場などのほか、バッグやベルトといった製品になる、天然の革材料を扱う伊藤登商店の倉庫を見学しました。創業昭和13年の「伊藤登商店」三代目で、石浜小の卒業生、伊藤勢一郎さんは「地場産業に革があるというのをちょっとでも覚えておいて欲しいという気持ちです。なかなか少ないとは思いますが、将来もちろん、この業界に入ればベストですけどね。でもやっぱり、浅草出身だけど、革は地場産業で、昔授業でやったんだよねっていうのを記憶に残しておいて欲しいなっていうのはあります」と話します。
下調べをけっこうしていたようで、伊藤さんは「実際に革を広げて、これが牛の半身で、こっちが頭でとか、ベルトはここを取るんですよ、っていうのを話しながら、普通に後は子供たちが質問をしてくるんですが、全部が直球の質問でした」と言います。一日どれくらい売れるんですか?なんでこの仕事を継いだんですか?仕事してて何が楽しいですか?伊藤さんは「仕事はつまらない」と最初は答え、「でも、仕事をしてお金をもらうわけだから、つまらなくならないよう、楽しむ努力をしてます」と説明したそうです。
また伊藤さんの紹介で、伊藤登商店の革材料の仕入れ先の一つ、栃木レザー社から後日、講師が学校に来て、生の動物の皮を、どういう「なめし」の技術を使って、革材料にするのか、授業で丁寧に教えたそうです。
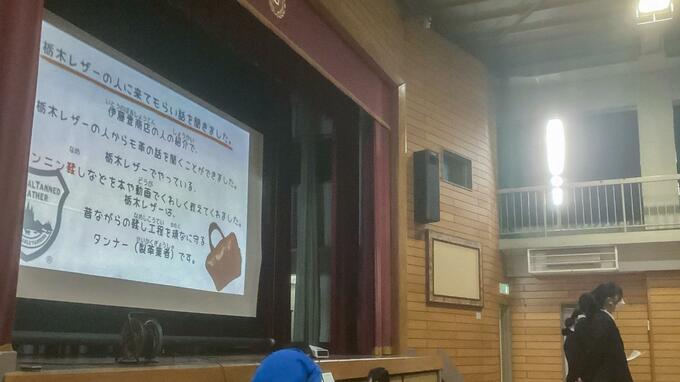
また、授業には歴史、そして人権の視点も入っています。東京都人権啓発センターの専門員が、江戸時代は、死んだ牛や馬を処理して取れる皮に関わる仕事をする人たちは差別された身分で、関東では、「弾左衛門」という人が浅草にいて、取りまとめていたことを解説しました。そして、明治になって身分制がなくなる一方で、皮革産業には誰もが関われるようになりましたが、弾左衛門たちも事業を続け、それは、現在の皮革産業の源流の一つであることなども説明しました。