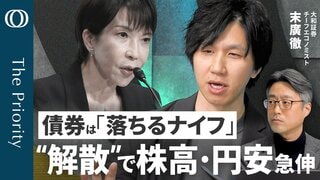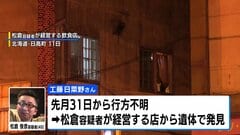(ブルームバーグ):人工知能(AI)ブームによるソフトバンクグループ株の急騰を当てた国内最大のテクノロジー株ファンドは、AI相場はこれから第2幕に入ると予想している。
AI向け半導体大手の米エヌビディアの時価総額が世界で初めて5兆ドル(約760兆円)を突破するなど、国内外の株式市場でテック株への投資人気が高まっている。一方、米S&P500種株価指数ウエートの3分の1以上を大型テック7社で占めるなど相場の一極集中や過熱に懸念も出始めており、AI株に対する読みの巧拙は今後の運用成績を左右する可能性がある。
野村アセットマネジメントの日本株投資信託「情報エレクトロニクスファンド」を運用する福田泰之チーフ・ポートフォリオマネージャーはブルームバーグのインタビューで、一部AI銘柄の動きに警戒はしているが、AI相場自体は「第2幕が始まったばかり」との認識を示した。
2000年のITバブル時は欧米テック株のアナリストだった福田氏は、足元のAI相場は「バブルという段階ではない」と分析。当時はパソコンや携帯電話の普及で通信量が劇的に増えた中、通信網への新規投資を行ったのはフリーキャッシュフローの乏しい企業で、バブル的なファイナンスが行われたことが問題だったと言う。
しかし今回は、クラウドコンピューティングで大規模な能力、容量を持ついわゆるハイパースケーラーがAI投資ブームを主導しており、「おおむね健全な企業の投資活動」だとみている。
福田氏は、AI普及に伴うデータセンター投資が成長の第1幕で、通信サービス事業者の大規模ネットワークへの負荷が増し、「投資を誘発するのが第2幕」だと指摘する。日本の電子部品や半導体関連メーカーにも恩恵が及ぶ可能性は高く、第2幕では通信事業者向けで強みを持つ古河電気工業に注目している。
1984年から40年以上の運用実績を持つ「情報エレクトロニクスファンド」は国内の電機や精密機器、情報ソフトサービス、通信関連企業を投資対象とし、福田氏が運用担当者となった2011年4月以降の成績は米ナスダック総合指数を上回る。就任時に72億円だった運用資産額は今年10月末時点で833億円と10倍以上に増え、エレクトロニクス系投信では国内最大規模だ。

同ファンドの25年のトータルリターンは11月6日時点でプラス49%と、運用資産総額が100億円以上の類似ファンド9本の中で上昇率トップ。同期間の東証株価指数(TOPIX、配当込みベース)の22%、TOPIX電機指数の30%を上回る。9月末時点の組み入れ銘柄上位はソフトバンクGやフジクラ、古河電工、ソニーグループ、東京エレクトロンなど。
ソフトバンクGについては24年5月に保有比率を大幅に増やし、1万円以下だった株価は今年10月に2万7000円台と最高値を更新した。子会社で半導体設計の英アーム・ホールディングスの成長性やAI革命への投資姿勢を評価しており、対話型AI「ChatGPT」のOpenAIなどと進める巨額のAI整備計画「スターゲート」は約80兆円に及ぶ日本政府の対米投資支援の中に盛り込まれる可能性があるとみる。
もっとも、ソフトバンクG株は主要アナリストの中で目標株価が最も高いみずほ証券の2万8000円に接近した後、急反落するなどAI関連銘柄は足元で不安定な動きも見せ始めた。
UBS SuMi TRUSTウェルス・マネジメントの小林千紗日本株ストラテジストは、長期的に心配していないと言う半面、OpenAIの投資上乗せなどから10月のAI株の上げが急激だったため、「米大手テック企業の好調な決算も出そろい、いったん利益確定があってもおかしくない」との見方も示した。
福田氏も、相場全体の底上げならいいが、米S&P500のように一部の銘柄だけにけん引された上昇には脆弱(ぜいじゃく)性があり、「この数カ月は日本も同じように質が良くないことは警戒している」と話している。
もっと読むにはこちら bloomberg.co.jp
©2025 Bloomberg L.P.