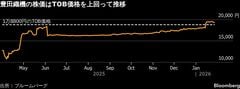「生成AI利用」日本は世界に遅れ 課題は…

喜入キャスター:
「生成AIサービス利用経験」(総務省24年度調査)について国別で見たデータがあります。
アンケート結果をみると、中国(81.2%)やアメリカ(68.8%)と比べて、日本(26.7%)は少し離されているんです。
小川キャスター:
世界から見ると遅れをとっているとも言えますが、中室さんはいかがですか。
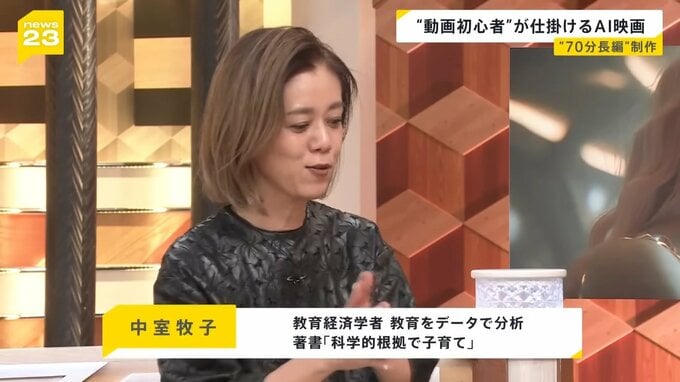
教育経済学者 中室牧子:
2つ理由があると思います。1つは、著作権や肖像権、知的財産の保護などの面で、グレーゾーンが多いので、日本の企業は法的リスクを恐れて、導入に二の足を踏んでいることが多いと言われています。
この問題に加えて、もう1つは「教育の問題」です。アメリカや韓国だと、高校や大学で生成AIを活用するための授業や講座などが始まっていますが、一方の日本は、大学の課題で生成AIを使うと不正行為になったり、あるいは単位を出さないといったところもあります。
つまり新しい技術に対して警戒感が強いなどの状況から、諸外国との間の差に繋がっているのではないかと思います。
小川キャスター:
そうした警戒感は、遠藤さんの中にはなかったですか。
クリエイター 遠藤久美子さん:
全くなかったですね。
マトリックスみたいに、頭にチューブがあって、カチャって開けて繋げられれば、私が見たビジョンを伝えられますが、それができないので。もうAIは本当に降ってきたチャンスだったなと思いました。「これでやっと表現できる」と。
小川キャスター:
その「原動力」はどこにあったのですか。
クリエイター 遠藤久美子さん:
やはり「このメッセージを伝えなければいけない」という使命感がすごくあったので、25年かけてやっとそれを表に出せると思ったので、ただただひたすらそのために時間を費やしました。
小川キャスター:
いろんなことにチャレンジしたいと思っても、なかなか二の足を踏んでできないという方もいらっしゃると思いますが、何かお伝えになりたいことはありますか。
クリエイター 遠藤久美子さん:
自分の中にそれぞれの物語を抱えていると思いますが、それを映像化できる時代になったことで、何か世界中に訴えたいメッセージがある人は、ぜひチャレンジしてみたらどうかなと思います。
小川キャスター:
中室さんはいかがですか。
教育経済学者 中室牧子:
映像制作は、結構特殊な世界だったのではないかなと思います。
テレビ業界で仕事をする中で学びましたが、カメラさんがいて、俳優さんがいて、台本を書く人もいる、さらに撮影をする場所も必要なわけですよね。かなりお金がかかるところだったのが、AIがあることで映像制作の世界に参入する障壁が低くなったと思います。
そうすると、まさに遠藤さんのような新しい才能が生まれて、新しい作品が生まれるきっかけになることは本当に素晴らしいことだと思いますね。
小川キャスター:
私も70分の作品を見させていただいて、やはりそのベースは人の力なんだなと感じました。何をどう表現するか、どのように生成AIを生かして活用するか。そこに人の力が試されるんだなと思いました。
クリエイター 遠藤久美子さん:
メッセージがあって、AIのツールがあって、ということは変わらないと思います。
========
<プロフィール>
遠藤久美子さん
4か月で70分のAI映画を制作
「AI日本国際映画祭」で特別招待上映
中室牧子さん
教育経済学者
教育をデータで分析
著書「科学的根拠で子育て」