(ブルームバーグ):トランプ米大統領は中国の習近平国家主席との首脳会談後、勝利を誇示するような口ぶりだった。しかし、1月の返り咲き以来初となった米中首脳会談では、得たものと同じくらい多くを譲る必要があった。
トランプ大統領は、難航していた争点で、中国が対米交渉で強い影響力を持つ分野でもあるレアアース(希土類)へのアクセス問題について、両首脳が「解決に至った」と表明した。大統領専用機「エアフォースワン」内で30日、「レアアースに関してはまったく障害はない」と述べ、「この言葉を当面、使わずに済むことを願っている」と語った。
トランプ氏が米国のみならず世界経済にとっての「勝利」と位置づけたのは、中国が重要鉱物の包括的な輸出規制の導入を1年間停止することに合意した点だった。これらの鉱物は、あらゆる産業にとって不可欠な資源だ。
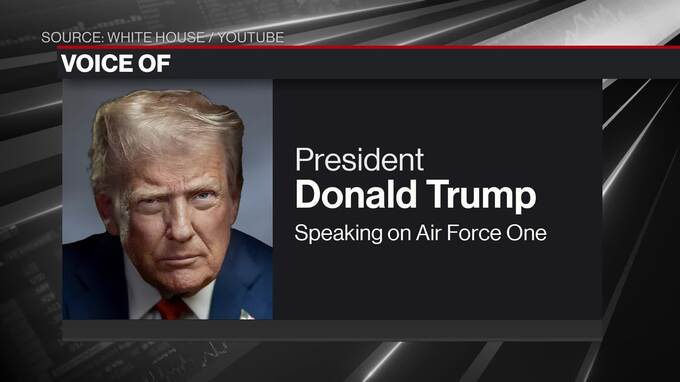
ただし、中国による新たな輸出規制は依然として用意されており、既存の規制も引き続き適用されている。そのため、米国を含む各国の企業は、戦闘機や半導体、電気自動車(EV)の製造に不可欠な重要部材の調達において、今後も中国の判断に左右される状況が続く見通しだ。この脅威を完全に取り除くには、世界の2大経済大国による、はるかに包括的な合意が必要とされる。
さらに、こうした中国側の猶予措置を引き出すために、トランプ氏も同様の譲歩を行わざるを得なかった。米国は中国企業数千社を新たに加える予定だった輸出規制対象リストの拡大を当面見送ることで合意した。
首脳会談から24時間以上が経過しても、ホワイトハウスは合意内容を示すファクトシートや書面による要旨を公表していない。一方、中国商務省は30日に文書を公表した。
米通商代表部(USTR)のグリア代表は、既存の規制について中国側から譲歩を引き出すことはできなかったと認め、今回の合意は過去の協議後に中国がほごにしてきた「未履行の約束」の延長に過ぎないとの見方を示した。
グリア氏は30日、ホワイトハウスで記者団に対し「今年導入された磁石向けのレアアース規制については、一定の流通が確保されていたが、今後はさらに円滑な供給が期待できる」とし、「中国側の対応もより包括的なものになると見込んでいる」と語った。
それでも米政府当局者は、今回の成果を世界とグローバル・サプライチェーンにとっての勝利であり、トランプ氏による成果だとアピールした。一方で、対中強硬派からの評価は限定的だ。
保守系シンクタンク、アメリカン・エンタープライズ研究所(AEI)の中国専門家、デレク・シザーズ氏は「中国が4月に磁石向け規制を導入して以来、米国の対中政策はドイツの長年の対中政策に似ている。いずれも中国に依存する一部の自動車メーカーによって動かされ、政府全体の方針を左右している」と指摘。「米国の場合は、自動車メーカーに加えて、中国に依存する大豆農家も含まれている点が独特だ」と語った。
危うい前例
今回の合意は、トランプ氏の2期目において中国が交渉上、より強い立場にあることを浮き彫りにした。事実上、米国は人工知能(AI)向け半導体などの先端技術輸出規制と、中国のレアアース規制とを交渉上リンクさせることを受け入れた形だ。ワシントンの対中強硬派の中には、これを危険なラインを越える行為だと見なす向きもある。
中国と先端技術分野に詳しいクリス・マグワイア氏は「中国によるレアアース規制は重大なエスカレーションであり、米国に追加規制を思いとどまらせようとする狙いがあった。そして米国は反撃する代わりに、自らの規制を緩和することに合意してしまった」と述べた。同氏はバイデン政権下で国家安全保障会議(NSC)に所属し、今夏まで国務省に勤務していた。
マグワイア氏は「こうしたことがこれまでに起きた記憶はなく、極めて危険な前例になる」と語った。今回の合意は新たな規制をめぐる1年間の「停戦」とも言える内容であり、米国の措置は対象が限定的なため、効果を維持するには頻繁な見直しが必要となるとし、その結果、「この合意は米国よりも中国に有利に働く」と指摘した。
中国は4月に初めてレアアース磁石の輸出規制を導入し、10月初旬には包括的な新方針を発表した。その間には双方による応酬が数カ月続いていた。
今週の会談を前に、トランプ氏は100%の関税引き上げを含む措置を示唆し、交渉での主導権を握ろうとした。しかし最終的には、この脅しに加え、中国のフェンタニル取引への関与を理由とした関税や、中国製の船舶が米国に寄港する際の料金も撤回した。これらの措置は、いずれも1年間凍結されることになった。
その結果、米国などのメーカーを中国から撤退させるために貿易障壁を利用するという大統領の狙いは、打撃を受ける可能性がある。トランプ氏が発表したとおり、フェンタニル関連の関税が20%から半減されれば、中国製品に対する平均関税率は31%に下がると、ブルームバーグ・エコノミクスは試算している。これは、ブラジルやインドからの多くの製品にかけられている50%を大きく下回る水準であり、少なくとも現時点では、中国での生産の方が両国よりも魅力的な状況となっている。
レアアース以外すべて
これら一連の譲歩は、トランプ氏の立場が弱まる可能性がある中で行われた。
連邦最高裁判所は来週、口頭弁論を開く予定で、この訴訟の結果次第では、新たな関税の大半が無効とされる可能性がある。下級審ではすでに、1977年の国際緊急経済権限法(IEEPA)に基づいた関税発動は違法だとの判断が下されている。この法律が関税の発動に使われたのは、今回が初めてだった。

もっとも、習氏も望んだ全てを手にしたわけではない。
トランプ氏は、米エヌビディアのAI向け半導体「ブラックウェル」の対中輸出について、会談前には承認の可能性を示唆していたが、最終的には踏み切らなかった。グリア氏は「現時点では」ブラックウェルは協議の対象にならなかったと述べたが、エヌビディアのジェンスン・フアン最高経営責任者(CEO)は31日、最終的には承認が得られるとの慎重ながら前向きな見方を示した。
トランプ氏が日本や韓国などとの協定で推進しているような、中国による米国への投資拡大を認める計画についても、具体的な内容は明らかにされなかった。
米中両首脳は2026年に一連の会談を行う計画を立てている。一方で、レアアース磁石に依存する産業や、中国に代わる供給網の構築を目指す企業にとって、今回の合意は大きな変化をもたらさない可能性もある。
米国で防衛用途などの磁石を製造するアドバンスト・マグネット・ラボのウェイド・センティ社長は「今回の米中休戦は、レアアースや永久磁石以外のことが大半だった」と述べた上で、「率直に言って、軍事分野におけるリスクは6月初めから何も変わっていない」と指摘した。
輸出許可
レアアースや磁石の輸入に依存する兵器や航空宇宙、自動車などの産業にとって現実となっているのは、中国の輸出規制が依然として状況を左右しているという事実だ。今年に入ってから何度も一時的な休戦や合意があったものの、実際の運用にはほとんど変化が見られない。
米企業に対する中国側の販売許可の手続きは依然として煩雑なままだ。輸出許可の承認までに時間がかかるケースが増えたと企業側は報告しており、中国政府は注文ごとに繰り返し申請書を提出させている。その影響は米国だけにとどまらない。ドイツなどの企業も現在では、許可を得るために機密性の高いサプライチェーン情報を中国当局に提出する必要に迫られている。
中国による新たな輸出規制の延期は、米産業界にとって一定の猶予となる可能性はある。例えば、防衛関連以外の企業にとっては、特定のレアアースや磁石の加工・生産に必要な重要機械の調達がしやすくなるかもしれない。
応酬の構図
ただ一部の専門家は、実際の運用では中国が輸出許可の発給を先延ばしにし、事実上の規制措置として機能させる可能性があると警鐘を鳴らしている。こうした手法は、米国が半導体の輸出許可で用いてきたやり方と同様だという。
業界関係者の間では、今回の米国の譲歩が、中国によるレアアース規制の実質的な見直しではなく、一時的な停止と引き換えになっただけではないかとの懸念が広がっている。さらに指摘されているのは、中国が包括的な措置の実施を先送りした一方で、問題の発端となった4月に導入された規制措置はいまだに継続中という事実だ。
トランプ政権1期目で商務省の高官を務め、現在はワイリー・レイン法律事務所でレアアースや永久磁石、半導体分野の企業を担当しているナザク・ニカフター氏は「中国が引き続き企業に許可申請を求め、従来のように審査を行わないのであれば、今回の動きはあまり前進を意味しない可能性がある」と述べた。
今回の合意には、レアアースをはじめとする中国関連の問題で、米国が過去にも時期尚早の勝利宣言をした経緯が影を落としている。例えば、グリア氏は7月にストックホルムでの交渉を終えた際、「もう二度と磁石の話はしたくない」と強い口調で述べた。
中国側がトランプ氏への対応に長けるようになってきたとの見方もある。
現在アジア・ソサエティー政策研究所に所属し、かつて米通商交渉官を務めたウェンディ・カトラー氏は「中国は譲歩のたびに代償を要求し、強気の交渉を展開した」と指摘。「トランプ氏は、互角に渡り合う中国に直面している。まさに応酬の構図だ」と語った。
原題:Trump Touts Rare-Earth Win in Talks Showing Xi’s Strong Hand (2)(抜粋)
--取材協力:Colum Murphy、Eric Martin.もっと読むにはこちら bloomberg.co.jp
©2025 Bloomberg L.P.
















