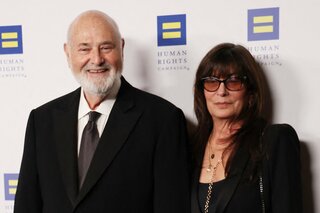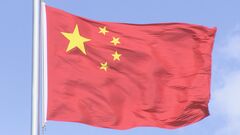その「自分の居場所がない」という感覚は、以後30年にわたる野田氏の政治活動の原点となった。男性が圧倒的多数を占める自民党内で女性の政治参加を促し、日本社会全体で女性が直面する困難を和らげようと取り組んできた。議事堂の環境は改善したものの、社会全体の男女平等の進展は依然として不十分だ。
日本は男女平等の世界ランキングで下位に低迷しており、特に政治参加や経済活動の指標での評価が低い。衆院議員のうち女性は約15%にとどまり、今週まで財務相に女性が就いたことは一度もなかった。日本銀行総裁も未だ男性のみで、政治を担当する記者もほとんどが男性だ。
こうした状況の中で、野田氏と同じ93年に初当選した高市早苗氏が日本初の女性首相に就任したことは、歴史的でありながら極めて例外的な出来事だ。男性中心の議場で深く一礼する姿は、女性の進出の象徴というよりも、いまだルールの例外であることを際立たせた。
もっとも、高市氏(64)が女性の権利向上を積極的に掲げているわけではない。それが今回の首相就任を多くの女性が冷静に受け止めている理由の一つでもある。
毎日新聞の政治記者出身で「オッサンの壁」の著者でもある佐藤千矢子氏によると、「今回の高市さんの選ばれ方というのはあまり女性という要素はなかった。高市さんというのは本当に女性というアピールをしない」という。「ジェンダー問題をほとんど言わなかった選挙でした」と振り返る。

高市氏はどんな人物か
61年生まれの高市氏は、奈良市の中流家庭に育った。両親が望んだ短大進学から安定した就職、早期結婚という道を拒み、アルバイトをしながら4年制大学で経営学を学んだ。大学ではヘビーメタルバンドでドラムを担当し、バイクにも熱中した。
大学教授やニュースキャスター、政治評論家を経て、93年に無所属で初当選。その後自民党に入党した。保守派である英国のマーガレット・サッチャー元首相を政治的な師と公言し、防衛・安全保障を中心とする著書を複数出版している。
2年前、自身のYouTubeチャンネルで、「私が出るころは、女が国会行って何するねんとかこの小娘がとか言われた」「仕事で結果出していくしかない。女性であることに甘えず、でも女性であることを捨てずというのは、私はずっと自分に言い聞かせてきた」と語った。
高市氏は10月4日、自民党総裁に選出された。石破茂首相の参院選大敗を受けた退陣表明に伴う総裁選挙で勝利。その後2週間をかけて連立体制を構築し、首相就任にこぎ着けた。同志社大学のジル・スティール教授は「危機のときに女性がリーダーに選ばれる『ガラスの崖』現象の典型だ」と述べ、「そのような状況では女性が成功しにくい」と分析する。
政策と政治的立ち位置
高市政権は、防衛強化や移民制限、外国資本規制の厳格化など、右派的政策を打ち出している。これは前回選挙で右派政党を支持した若年男性層の取り込みを狙った動きでもある。
高市氏は保守色が強く、安全保障・社会政策における立場は男性層に響きやすい。サッチャー氏と同様、フェミニズム運動からは距離を置く。今月初めに「私自身ワークライフバランスという言葉を捨てます。働いて、働いて、働いて、働いて、働いてまいります」と発言し、長時間労働と育児の両立に苦しむ家庭が多い日本では批判も起きた。
同性婚の法制化や夫婦別姓の容認にも反対しており、家族の一体性を損なう恐れがあると主張する。党総裁就任直後には、公明党が政策の違いを理由に連立を離脱。高市氏は男女平等を重視しない保守的な政党と新たに連携した。
首相就任後の記者会見で、閣僚に女性を2人しか起用しなかった理由を問われた高市氏は「当初より申し上げております通り、私は、あくまでも機会平等、チャンスの平等、これを大事にしています。それから全員参加、全世代総力結集、この考えで組閣を行いました」と答えた。
世界と日本の女性リーダー
第2次世界大戦後の米国占領期に女性参政権と男女平等が導入された日本で、ようやく女性首相の誕生が実現した。190を超える国連加盟国うち女性リーダーを持つ国は約3分の1に過ぎず、昨年時点で現職の女性首脳は13人(ピュー・リサーチ・センター調べ)。米国では依然として女性大統領は誕生していない。
日本でも野党では女性が要職を務めた例がある。土井たか子氏は86年に社会党委員長に就任し、同一世代の女性を鼓舞した。しかし、自民党内で女性が台頭した例は少ない。
小池百合子前環境相は、日本の女性政治家が直面する壁について「鉄の天井」と表現した。2016年、党内での行き詰まりを経て国政を離れ、東京都知事選に出馬して当選。男性中心の政治構造を批判したことで多くの女性支持を得ており、現在3期目を務めている。
今後の課題
上智大学の三浦まり教授は「今回の女性首相誕生は不祥事続きの自民党にとってイメージ刷新になる」とし、「一定のハネムーン期間はあるだろう」と分析する。一方、「その後は性別ゆえに男性より厳しい批判を受ける」とみる。
日本の女性登用は経済界でも遅れている。東証上場企業の取締役に占める女性比率は14.8%にとどまり、その多くは社外取締役だ。18年には複数の医科大学で女性受験者を不正に排除していたことが発覚し、女性が離職しやすいという理由で男性を優遇していたことが明らかになった。
伝統の領域でも女性の排除は続く。大相撲では土俵に女性が上がることを禁じている。18年には京都府舞鶴市で行われた巡業の土俵上であいさつをしていた市長が脳出血で倒れた際、救命処置をした女性が土俵から退去を命じられ、批判が集中した。
皇位継承でも、女性天皇の容認を巡る議論が長年続いている。高市政権は、皇統維持のために男系の遠縁を皇族に復帰させる案を支持している。
閣僚に占める女性は高市首相を除いて2人にとどまる。過去最多は5人だったが、今回は初めて女性財務相が誕生した点が注目される。もう1人の女性閣僚は経済安全保障と外国人政策を担当する。
女性たちの受け止め
JPモルガン証券の日本株ストラテジスト、西原里江氏は政策面でも社会面でも新政権には期待しているという。「政治は多様性の遅れた分野だからこそ、女性首相の存在自体が企業や社会の多様性を自然に広げる」とみている。
一方、野田氏は21年の自民党総裁選で高市氏と争い、今回は小泉進次郎氏を支持した。「ガラスの天井をポンと破っていただいたのはすごいこと」「私も謙虚になぜ自分はそこまで行けなかったと反省しながらまたコツコツ自分の得意分野をいかす」とX(旧ツイッター)に音声コメントを投稿した。

もっと読むにはこちら bloomberg.co.jp
©2025 Bloomberg L.P.