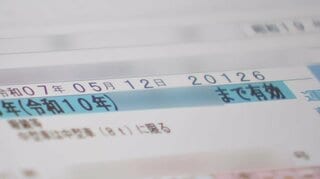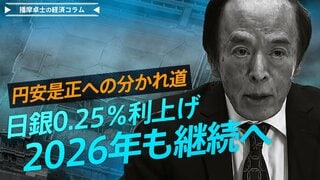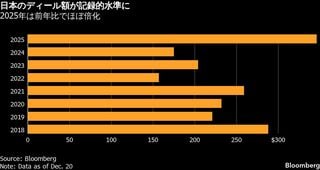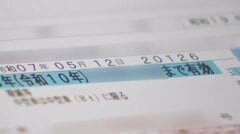(ブルームバーグ):国民民主党の玉木雄一郎代表(56)は所得税の発生する「年収の壁」の引き上げといった政策で現役世代の支持を得てきた。野党統一候補として名前の挙がる首相への意欲も隠さない。
「2020年の結党以来、国民民主党は一貫してまじめに働く人の給料を上げる、手取りを増やす政策を訴えてきた」。玉木氏は7月の参院選で、物価高に苦しむ国民の可処分所得を増やす経済政策を前面に訴えてきた。比例代表では立憲民主党を超え、自民党に次ぐ2番目の得票を得た。
来週にも行われる首相指名選挙では、玉木氏の動向が最大の焦点だ。立民は玉木氏を野党統一候補に擁立することも検討しているが、玉木氏は立民に安全保障政策などの見直しを求めており、調整が難航する可能性もある。
「内閣総理大臣を務める覚悟はある」とも明言する同氏だが、21日の国会召集を前にぎりぎりの交渉が続きそうだ。
玉木氏らがかつて所属した民主党が政権を失ってから約12年。公明党の連立離脱で野党に政権奪取の機会が訪れているが、統一候補で合意できるかは依然不透明だ。玉木氏は15日午後、立民、日本維新の会との党首会談に臨む。
年収の壁引き上げ
昨年の衆院選でも「手取りを増やす」をキャッチフレーズに掲げ、年収の壁引き上げやガソリン税の暫定税率廃止を目玉に据えた。現役世代支援を前面に出した政策が受け入れられ、議席を4倍増。与党が過半数割れする中、存在感を一躍高めた。
若年層の支持を集めた要因の一つにSNSを駆使した戦術がある。動画配信でシャツの袖をまくりながら経済政策を説明したり、選挙期間は移動中の車内からフォロワーに語り掛ける姿が共感を生んでいるようだ。
衆院選直後には不倫疑惑が報じられ、役職停止3カ月の処分を受けた。その後、活動を再開して臨んだ7月の参院選でも「手取りを増やす夏」と訴え、議席を伸ばした。現在は衆院で27議席、参院で25議席の勢力となった。
財務官僚から政界へ
1969年、香川県の兼業農家の長男として生まれた。東大法学部を卒業し、財務省に入省。同期に自民党の木原誠二元官房副長官がいる。一度の落選を経て当時の民主党から2009年の衆院選で初当選した。政権交代で与党として国会議員生活を始めたが、3年後の衆院選で党は野党に転落する。
安倍晋三政権が続く中、安全保障法制への対応などを巡って民主党は対決姿勢で臨み、共産党との連携も進める。16年に旧みんなの党出身者らが合流した民進党が誕生したが、「批判一辺倒の万年野党化という悪い方向に歩み始めたように見えた」と今年3月に出版した著書で振り返った。
大きな転機となったのは小池百合子東京都知事が17年に設立した希望の党への参加だ。党は衆院選で大敗したが、衆院選後に代表に就任。18年には民進党に残留していた参院議員らが合流し旧国民民主党を結成したが、党勢は伸び悩む。
新・国民民主党
20年には泉健太氏ら多くの仲間が立民に移り、衆参15人で現在の国民民主党として再出発。立民に見直しを求めている安全保障やエネルギー政策では政権獲得を見据え、現実路線に転換した。
玉木氏は10日、現在の国民は、旧民主党的なものを一度否定して、安保、エネルギー、経済政策で「それまでの路線といったん決別をした上で未来思考の新しいスタートを切った」と説明した。
22年に策定した文書で「現実的平和主義」を基本理念に掲げ、自衛のための打撃力(反撃力)の保持や、必要な防衛費を増額する方針を明記した。集団的自衛権の行使を一部認める安全保障法制は「内容にも手続きにも問題」があったとしつつ、日米間では同法制に基づいた体制整備が行われていると容認する姿勢を示した。
玉木氏は13日、X(旧ツイッター)への投稿で、日本の現在の防衛体制の基盤となっているのは安保法制だと指摘。国民民主は現行法制を前提に「同盟国・同志国と連携し、日本を守り抜く覚悟と具体的政策」を持っていると主張している。

エネルギー政策についても立民とは隔たりがある。国民は原子力発電所や再稼働や新増設などで安定的な電力確保を主張。立民は「原発ゼロ社会」の早期実現を綱領で掲げており、原発の扱いも両党間ですり合わせが必要になっている。
高圧経済
経済財政運営に関しては「未来志向の積極財政」を志向している。25年の政策集にも、財政健全化目標の見直しと実質賃金上昇率が2%に達するまで、積極財政と金融緩和による「高圧経済」を行う方針を明記。子育て支援のために「教育国債」の発行も唱えた。

仮に玉木氏が首相に就任すれば財政支出の拡大も想定されるが、同党は財源確保手段として日本銀行が保有する国債の一部を永久国債に転換する案を政策集に盛り込んでいる。
同案について、自民党の鈴木俊一幹事長は財務相時代の22年、政府が日銀の機能を利用して財政調達を行うことになると考えられ「財政ファイナンスとのそしりを受ける懸念がある」との見解を示している。
一方、金融政策に関しては、経済が悪化すれば金融緩和を検討する余地があると今年4月に発言していたが、10月7日の記者会見では「金融政策は日銀がいろいろな指標を見ながら、適切に判断していくことになる」と述べるにとどめた。
もっと読むにはこちら bloomberg.co.jp
©2025 Bloomberg L.P.